漢詩紹介
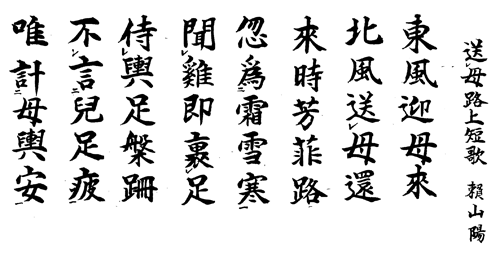
読み方
- 母を送る路上の短歌(2-1)<賴山陽>
- 東風に 母を迎えて來り
- 北風に 母を送りて還る
- 來る時は 芳菲の路
- 忽ち 霜雪の寒と爲る
- 鶏を聞いて 即ち足を裹み
- 輿に侍して 足槃跚たり
- 兒の足の 疲るるを言わず
- 唯母の輿の 安きを計る
- ははをおくるろじょうのたんか<らいさんよう>
- とうふうに ははをむかえてきたり
- ほくふうに ははをおくりてかえる
- きたるときは ほうひのみち
- たちまち そうせつのかんとなる
- とりをきいて すなわちあしをつつみ
- こしにじして あしはんさんたり
- じのあしの つかるるをいわず
- ただははのこしの やすきをはかる
字解
-
- 芳 菲
- 草花の良い香り
-
- 裹 足
- 足に脚絆や草鞋をつける 足ごしらえをする
-
- 侍 輿
- 駕籠のそばに仕える
-
- 槃 跚
- 足がふらつく
意解
春風が吹くころに母を京都に迎え、北風の吹く冬に母を送って広島に還る。
来る時は道中いたる所に良い香りのする草花が咲き匂っていたのに、今はもう霜や雪の降る寒い時節となった。
朝一番の鶏の声を聞くや足ごしらえをして母の駕籠に付き添っていくが、自分は疲れて足がふらついている。
しかし自分の足が疲れたことは口には出さず、ただ母の駕籠が無事であることを案ずるばかりである。
備考
この詩は文政12年(1829)2月、父春水の十三回忌の法要のため広島へ帰り、3月7日母を奉じて京都に至り、各地を見物、10月20日京都を出発し尾道まで送る(それより先は母を再従弟=またいとこ=に託した)その時の路上の所感である。
詩の構造は五言8句と七言6句とで構成された古詩の形であって、韻は上平声十五刪(さん)韻の還と上平声十四寒(かん)韻の寒、跚、安、乾、難 、歡の字が通韻して使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
参考
「山陽道」について
五畿七道の一。播磨(はりま)・美作(みまさか)・備前・備中・備後・安芸(あき)・周防(すおう)・長門(ながと)の8カ国を通ずる街道。
