漢詩紹介
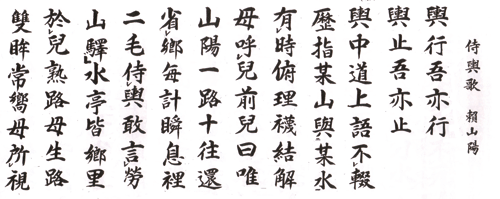
読み方
- 侍輿の歌<賴山陽>
- 輿行けば 吾も亦行き
- 輿止まれば 吾も亦止まる
- 輿中道上 語って輟まず
- 歴指す 某山と某水と
- 時有って俯して理む 襪結の解くるを
- 母兒を呼んで前ましむれば 兒曰く唯と
- 山陽一路 十たび往還
- 郷に省れば毎に計る 瞬息の裡
- 二毛輿に侍して 敢えて勞を言わんや
- 山驛水亭 皆郷里
- 兒に於ては熟路なるも 母には生路
- 雙眸常に嚮こう 母の視る所に
- じよのうた<らいさんよう>
- こしゆけば われもまたゆき
- こしとどまれば われもまたとどまる
- よちゅうどうじょう かたってやまず
- れきしす ぼうざんとぼうすいと
- ときあってふしておさむ ばっけつのとくるを
- ははじをよんですすましむれば じいわくいいと
- さんよういちろ とたびおうかん
- きょうにかえればつねにはかる しゅんそくのうち
- にもうこしにじして あえてろうをいわんや
- さんえきすいてい みなきょうり
- じにおいてはじゅくろなるも ははにはせいろ
- そうぼうつねにむこう ははのみるところに
字解
-
- 侍 輿
- 駕籠のそばにお仕えする
-
- 歴 指
- いちいちはっきり指し示す
-
- 俯 理
- うつむいて結び直す
-
- 襪 結
- 結び紐
-
- 唯
- 「はい」という返事
-
- 二 毛
- 白髪混じり
-
- 生 路
- はじめての路
意解
母の乗っておられる駕籠が行くと自分もまた進み、駕籠が止まると私も止まる。
駕籠の中の母と路上の私はずっと語り合って止む時が無く、山や川を指差しては「これは何という山、あれは何という川」という風に説明する。
ある時には足の紐が緩んだのをうつむいて結び直していると、母は私に「早く進みなさい」と声をかけられるので、私はその都度「はい」と答えながら駆け寄って行く。
一筋道の山陽道を私はもう十回も往復しているが、帰省に際してはいつもその行程はできるだけ短時間であるように心がけてきた。(しかし今回は十分ゆっくり旅程を計画した)
白髪混じりの年になって、母の駕籠に付き添うのは正直きついけれどどうして辛いなどといえようか。それは山中の宿場や水辺のあずまやが自分にはなじみ深く、皆故郷のようなもので、その中で親孝行ができるのだから。
この道は自分にとっては慣れた道だが、母にとっては初めての道なので、母が珍しそうにあちこちご覧になるその視線の方向を、自分の二つの目でいつも追っては、お相手しながら行くのである。
備考
この詩は文政2年(1819)2月郷里に帰り、母を奉じて京都へ行く時の作である。本題は「余到芸留数旬將 帰京寓。遂奉母偕行。作侍輿歌」(余芸に到り留まること数旬將に京寓に帰らんとす。遂に母を奉じて偕=とも=に行く。侍輿の歌を作る)であるが 本会では「侍輿歌」と簡略にした。詩の構造は古詩の形であって上声四紙(し)韻の止、水、唯、裡、里、視の字が使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳で京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
