漢詩紹介
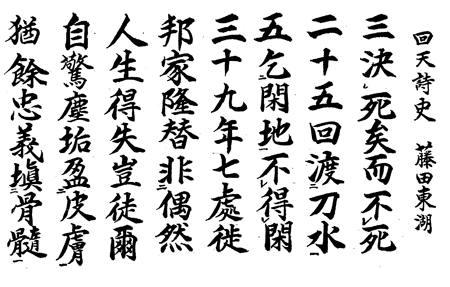
読み方
- 回天詩史(2-1)<藤田東湖>
- 三たび死を決して 而も死せず
- 二十五回 刀水を渡る
- 五たび閑地を乞うて 閑を得ず
- 三十九年 七處に徙る
- 邦家の隆替 偶然に非ず
- 人生の得失 豈徒爾ならんや
- 自ら驚く塵垢の 皮膚に盈つるを
- 猶餘す忠義の 骨髓を填むるを
- かいてんしし<ふじたとうこ>
- みたびしをけっして しかもしせず
- にじゅうごかい とうすいをわたる
- いつたびかんちをこうて かんをえず
- さんじゅうきゅうねん しちしょにうつる
- ほうかのりゅうたい ぐうぜんにあらず
- じんせいのとくしつ あにとじならんや
- みずからおどろくじんこうの ひふにみつるを
- なおあますちゅうぎの こつずいをうずむるを
字解
-
- 回 天
- 天を回転させる 天下の形勢を変える
-
- 刀 水
- 利根川 刀寧川とも書くので略して刀水という
-
- 邦 家
- ここでは水戸藩
-
- 隆 替
- 盛んになることと衰える
-
- 人生得失
- 人の世の得意と失意
-
- 徒 爾
- ただごと いたずら 「爾」は助字
-
- 塵 垢
- ちりとあか
-
- 填
- 溢れている
-
- 骨 髓
- ここでは満身
意解
過去を回想すれば死を決心したことが3度あったが、死ぬことが出来なかった。江戸と水戸を往復して利根川を25回も渡った。
職を辞めて閑地につこうと5回願い出たが許されず、そして39年の間に7ヵ所に転居した。(ただ身命を賭して己の信ずるところに邁進したためである)
国家の盛衰は偶然にそうなるのではなく、起こり得るものであって、人生の得意と失意も徒(いたず)らごとではない。
このように信ずる道を行ったつもりであったが、ついに幽囚の身となり、塵と垢が積もってしまったことに驚き、それでもなお忠義を尽くそうとする誠心は満身に溢れている。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、韻は上声四紙(し)韻の死、水、徙、爾、髓、企、起、已の字が使われ、一韻到底格である。
作者略伝
藤田東湖 1806-1855
幕末期の水戸藩士。尊皇攘夷推進派の巨頭。名は彪(たけき)、字は斌卿(ひんけい)、東湖は号。幼名武次郎、虎之介と称し、のち藩主より誠之進の名を賜る。水戸藩儒官藤田幽谷の子で幼時より文武の修練に励み、父の死後彰考館(しょうこうかん)に入り一時総裁代理となる。藩主徳川斉昭をたすけ藩政改革に尽力。藩校弘道館設立は藩主斉昭と共に成し遂げたものであり、水戸学を振興しその中心人物となった。遺(のこ)された「弘道館記」は東湖の草案によるものである。安政2年10月に起こった大地震の時、母親を助けようとして逃げ遅れ圧死した。年50。「回天詩史」他著書多し。
