漢詩紹介
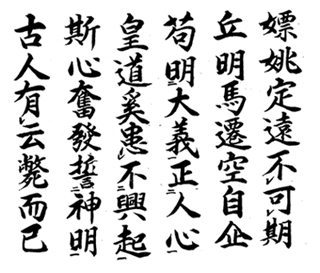
読み方
- 回天詩史(2-2)<藤田東湖>
- 嫖姚定遠 期す可からず
- 丘明馬遷 空しく自ら企つ
- 苟しくも大義を明らかにして 人心を正さば
- 皇道奚ぞ 興起せざるを患えん
- 斯の心奮發して 神明に誓う
- 古人云う有り 斃れて已むと
- かいてんしし<ふじたとうこ>
- ひょうようていえん きすべからず
- きゅうめいばせん むなしくみずからくわだつ
- いやしくもたいぎをあきらかにして じんしんをたださば
- こうどうなんぞ こうきせざるをうれえん
- このこころふんぱつして しんめいにちこう
- こじんいうあり たおれてやむと
字解
-
- 嫖 姚
- 前漢の将軍霍去病(かくきょへい) 武帝の時に匈奴を征伐した
-
- 定 遠
- 後漢の将軍班超 班固の弟で西域諸国を平定した
-
- 丘 明
- 魯の歴史家左丘明 「春秋左氏伝」の著者
-
- 馬 遷
- 前漢の歴史家司馬遷 「史記」の著者
意解
幽囚の身では霍去病や班超のように大軍を指揮して外夷を撃つようなことは期待できないけれど、できれば左丘明や司馬遷のように歴史を述べ善悪を明らかにしたいものと考えている。
かりにも大義を明らかにし天下の人心を正すことができたら、政道も自ずから正しくなり皇道の興らないことを心配する必要はない。
この心をもって一層奮起することを天地神明に誓うものである。古人も言っているように自分も斃れて後已むの覚悟である。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、韻は上声四紙(し)韻の死、水、徙、爾、髓、企、起、已の字が使われ、一韻到底格である。
作者略伝
藤田東湖 1806-1855
幕末期の水戸藩士。尊皇攘夷推進派の巨頭。名は彪(たけき)、字は斌卿(ひんけい)、東湖は号。幼名武次郎、虎之介と称し、のち藩主より誠之進の名を賜る。水戸藩儒官藤田幽谷の子で幼時より文武の修練に励み、父の死後彰考館(しょうこうかん)に入り一時総裁代理となる。藩主徳川斉昭をたすけ藩政改革に尽力。藩校弘道館設立は藩主斉昭と共に成し遂げたものであり、水戸学を振興しその中心人物となった。遺(のこ)された「弘道館記」は東湖の草案によるものである。安政2年10月に起こった大地震の時、母親を助けようとして逃げ遅れ圧死した。年50。「回天詩史」他著書多し。
