漢詩紹介
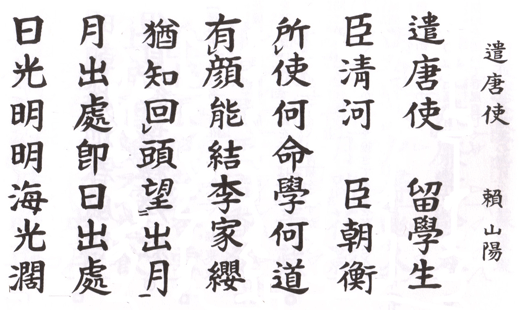
読み方
- 遣唐使<賴山陽>
- 遣唐使 留學生
- 臣淸河 臣朝衡
- 使いする所は 何の命ぞ 學ぶ何の道ぞ
- 顔あり能く結ぶ 李家の纓
- 猶知る頭を回らして 出月を望む
- 月出ずる處即 日出ずる處
- 日光明明 海光濶し
- けんとうし<らいさんよう>
- けんとうし りゅうがくせい
- しんきよかわ しんちょうこう
- つかいするところは なんのめいぞ まなぶなんのみちぞ
- かんばせありよくむすぶ りかのえい
- なおしるこうべをめぐらして しゅつげつをのぞむ
- つきいずるところすなわち ひいずるところ
- にっこうめいめい かいこうひろし
字解
-
- 遣唐使
- 推古天皇の御世に初めて中国(唐)に使者を遣わされ 宇多天皇の御世まで およそ300年間 引きつづいて使者と留学生とを遣わされる 隋のときには遣隋使と言い 唐の時には遣唐使と言う
-
- 臣淸河
- 藤原清河のこと 勝宝3年遣唐使として往く
-
- 臣朝衡
- 阿倍仲麻呂のこと 唐朝に仕え名を朝衡とした
-
- 李家纓
- 唐朝の姓が李 玄宗は李隆基である 纓は冠の紐のこと 唐朝の衣冠をつけて仕えた事を言う
-
- 望出月
- 仲麻呂明州に至り明月を望み 悵然として「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌を詠じた
-
- 日光明明
- 日光をもって皇徳にたとえる
意解
遣唐使又留学生は、何の為に彼の国に使いし、如何なる道を学ぶ為に行ったのであるか。己の使命を忘れ、己の本分を忘れて、唐朝の衣冠を着け、唐朝の禄を食むとは何というよい面の皮であろう。とは言え「天の原…」の歌を詠んだのを見れば、全く祖国を忘れたと言うのでもないようである。その月の出ずる処は即ち日の出ずる処であり、日の出ずる処即ち我が日の本の国である。そして我が日本の皇統は、明々たる光と共に千秋萬古限りなく、また窮まりなく四海を照らしているのである。
備考
楽府(がふ)とは、もと漢の時代に音楽をつかさどるところとして設けられた官庁の名であるが、この官庁が作り または採取した歌謡のたぐいで、楽器の伴奏で演奏されたものをも、楽府と呼ぶようになった。一篇の詩は何句という句数はなく、一句も何字と定った 字数はない。文学的表現等装飾を重点とせず内容に重点を置く。
C23号掲載の3詩は日本楽府とよぶ。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳で京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府」などがある。
