漢詩紹介
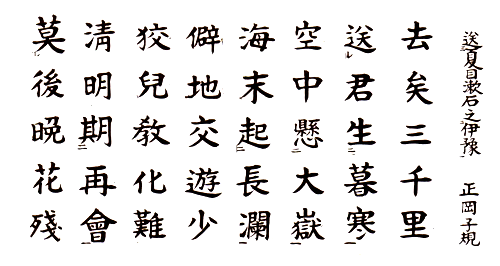
読み方
- 夏目漱石の伊豫に之くを送る<正岡子規>
- 去けよ 三千里
- 君を送れば 暮寒生ず
- 空中に 大嶽懸り
- 海末に 長瀾起こる
- 僻地は 交遊少に
- 狡兒の 教化は難し
- 淸明には 再會を期せん
- 後るる莫れ 晩花の殘るうちに
- なつめそうせきのいよにゆくをおくる<まさおかしき>
- ゆけよ さんぜんり
- きみをおくれば ぼかんしょうず
- くうちゅうに たいがくかかり
- かいまつに ちょうらんおこる
- へきちは こうゆうまれに
- こうじの きょうかはかたし
- せいめいには さいかいをきせん
- おくるるなかれ ばんかののこるうちに
字解
-
- 大 嶽
- 大きな山 ここでは富士山
-
- 海 末
- 海のはし ここでは瀬戸内海
-
- 長 瀾
- 大きな波
-
- 狡 兒
- わるがしこい いたずらな生徒
意解
さあ、出かけなさい、遠い四国の松山へ。元気づけて君を見送れば淋しさがおそい、夕暮れの寒さが身にしみる。
東海道を下れば空高く霊峰富士を仰ぎみることができ、また瀬戸内の大波も見ることができるであろう。
僻地での君には心おきなくつき合える友が少なく、その上いたずらな生徒の教育はさぞむずかしいに違いない。
君とは清明の頃に是非ともお逢いしたい。せめて遅咲きの春の花が散りうせぬうちに。
備考
この詩の構造は仄起こり五言律の形であって、上平声十四寒(かん)韻の寒、瀾、難、殘の字が使われている。
作者略伝
正岡子規 1867-1902
愛媛県松山に生まれた。本名は常規(つねのり)、字は獺祭書屋(だっさいしょおく)主人・竹の里人(さとびと)。俳人であり歌人。「獺祭書屋俳話」は明治25年、「歌よみに与ふる書」は明治31年に、新聞「日本」に掲載。雑誌「ホトトギス」を創刊。没後「アララギ」へと発展する。明治35年36歳で没す。
