漢詩紹介
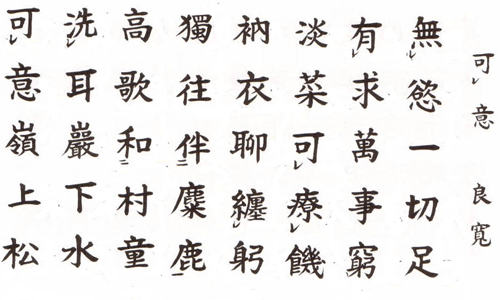
読み方
- 意に可なり<良寬>
- 慾無ければ 一切足り
- 求むる有れば 萬事窮す
- 淡菜 饑を療す可く
- 衲衣 聊か躬に纏う
- 獨り往いて 麋鹿を伴とし
- 高歌して 村童に和す
- 耳を洗う 巖下の水
- 意に可なり 嶺上の松
- こころにかなり<りょうかん>
- よくなければ いっさいたり
- もとむるあれば ばんじきゅうす
- たんさい うえをいやすべく
- のうい いささかみにまとう
- ひとりゆいて びろくをともとし
- こうかして そんどうにわす
- みみをあろう がんかのみず
- こころにかなり れいじょうのまつ
字解
-
- 衲 衣
- 衲はころも また僧の自称 僧の衣類を表す
-
- 麋 鹿
- 麋はおおしか おおしかと鹿と
-
- 洗 耳
- 堯帝(ぎょうてい)の時 位を許由(きょゆう)に譲ろうとしたところ 許由はけがらわしい事を聞いたと川の水で耳を洗った相伝の故事に基づく
意解
欲がなければ、すべて足りて不足ということはない。求めようとするから、万事きわまるのである。
粗食でもうえをいやすことができ、粗末な衣でもどうにか寒さをしのぐことができる。
独り鹿をつれながら、自然にひたり、また村におりては子供達と声をあげて歌いあう。
岩の下には清らかな水が流れていて、俗事のけがれを洗うことができる。嶺上の松風は仏の声となって私の意(こころ)を満たしてくれる。
備考
この詩の構造は五言古詩の形であって上平声一東(とう)韻の窮、躬、童と上平声二冬(とう)韻の松の字が通韻 して使われている。
作者略伝
良 寬 1758-1831
江戸時代末期の僧侶。本姓山本、幼名栄蔵(えいぞう)、のち文孝(ふみたか)と改めた。字は曲(まがり)、出家して良寬また大愚(たいぐ)と号した。越後(新潟県)出雲崎の人。家は代々神職と名主(なぬし)を兼ね父泰雄は以南(いなん)と号して越後俳壇の雄であった。良寛はその長子。成長して備中(岡山県)玉島の国仙和尚(こくせんおしょう)に学び、のち諸国を行脚(あんぎゃ)して帰国し国上山(くがみやま)の五合庵に入り、47歳から13年間ここに住んだ。晩年麓の乙子(おとご)神社の庵に移り天保2年1月貞信尼(ていしんに)に看取られ歿す。時に74歳。良寬は俳句、短歌に一家をなし書もまた当代第一と称せられた。
