漢詩紹介
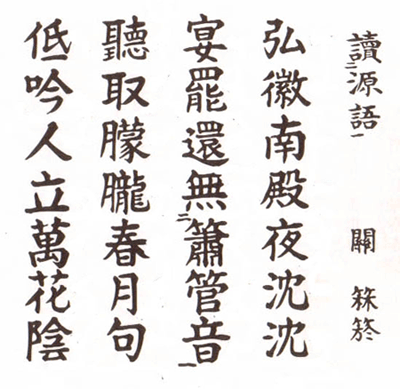
読み方
- 源語を讀む<關 箖箊>
- 弘徽南殿 夜沈沈
- 宴罷み 還た 簫管の音無し
- 聽き取る朦朧 春月の句
- 低吟人は立つ 萬花の陰
- げんごをよむ<せき りんお>
- こきなんでん よるちんちん
- えんやみ また しょうかんのおとなし
- ききとるもうろう しゅんげつのく
- ていぎんひとはたつ ばんかのかげ
字解
-
- 讀源語
- 源氏物語を読んでの作 この詩は「夕顔」「花宴(はなのえん)」二首のうちの「花宴」
-
- 弘 徽
- 弘徽殿(こきでん) 京都御所清涼殿の北にある平安京内裏の殿舎のひとつ 又そこに住む皇后、中宮、女御(にょ ご)などの称
-
- 簫 管
- しょうのふえ
-
- 朦 朧
- おぼろ
-
- 春月句
- 弘徽殿の廊下で聞いた若い女性の「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜(おぼろづきよ)に似るものぞなき」の 歌
-
- 低 吟
- 低く小さな声で歌う
意解
弘徽殿の南殿の夜はふけわたり桜の宴も終り簫管の音もなくなりました。源氏の君が廊下を歩いていると「……朧月夜に似るものぞなき」と口ずさむ若い女性の声が聞こえとても心をひかれました。低吟の人は万花の陰に立っているらしかった。という詩意。
源氏物語ではその夜ひとときを過ごした女性はどこの誰かも言わずに帰って行きました。その後右大臣の藤の花見にさそわれた源氏の君はあの女性 (朧月夜)が姫宮達のそばに居るに違いないと「梓弓いるさの山にまどふかなほのみし月の影や見ゆると」(ちらと見た月の姿がふたたび見られよう かといるさの山に迷っています)とよむと御簾(みすだれ)のうちから「心いる方なりませば弓張の月なき空に迷はましやは」(深くお心にかけておい でなら月のない空でもお迷いになるはずはありますまいに)と弘徽殿の月夜に聞いたのと同じ声で返ってきました。再会出来た源氏の君はうれしくてならないのでした。
備考
この詩の構造は平起こり七言絶句の形であって、下平声十二侵(しん)韻の沈、音、陰の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
關 箖箊 ?-1875
名は千代(ちよ)。江戸下谷(したや)に生まれ幼少より学を好み詩書をよくした。父の思亮(しりょう)は書家として知ら れ弟雪江(せっこう)は特に有名である。父が死去したとき弟は幼かったのでこれを養育し、弟も箖箊を母の如く慕い仕えたという。明治5年政府が 女学校を創設したとき箖箊を教諭とした。在職4年で明治8年死去した。
