漢詩紹介
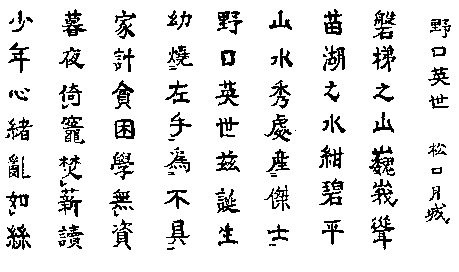
読み方
- 野口英世(6-1)<松口月城>
- 磐梯の山は 巍峨として聳え
- 苗湖の水は 紺碧平らかなり
- 山水秀ずる處 傑士を産む
- 野口英世 茲に誕生
- 幼にして左手を 燒きて 不具と爲る
- 家計貧困にして 學ぶに資無し
- 暮夜竃に椅りて 薪を焚いて讀む
- 少年の心緒 亂れて 絲の如し
- のぐちえいせい<まつぐちげつじょう>
- ばんだいのやまは ぎがとしてそびえ
- びょうこのみずは こんぺきたいらかなり
- さんすいひいずるところ けっしをうむ
- のぐちえいせい ここにたんじょう
- ようにしてさしゅを やきて ふぐとなる
- かけいひんこんにして まなぶにしなし
- ぼやかまどによりて たきぎをたいてよむ
- しょうねんのしんしょ みだれて いとのごとし
字解
-
- 磐梯山
- 猪苗代湖(福島県)の北にそびえる標高1819メートルの名峰
-
- 巍 峨
- 高く聳える
-
- 苗 湖
- 猪苗代湖 磐梯山の麓にある
意解
磐梯山は天高く聳え、猪苗代湖の水は青々と広がっている。
このような山水の秀でた地に偉大な人、即ち野口英世が誕生した。
幼くして左手に火傷を負い、不自由な身となったうえ、家計は貧困で学問するにも学資がなかった。
だから日が暮れると竈のそばで薪を焚いてその明かりで読書したりしたが、少年の心は将来のことを思うと、もつれる糸のように乱れていた。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、韻は次の通りである。
第2・4句 下平声八庚(こう)韻の平、生
第6・8句 上平声四支(し)韻の資、絲
第10・12句 上平声十一眞(しん)韻の諄、人
第13~16句 下平声十一尤(ゆう)韻の休、洲、秋
第18・20句 去声九泰(たい)韻の會、大
第22・24句 下平声八庚(こう)韻の聲、榮
第26・28句 上平声四支(し)韻の姿、離
第30・32句 下平声八庚(こう)韻の情、聲
第34・36句 入声九屑(せつ)韻の烈、傑
第37~40句 下平声八庚(こう)韻の驚、征、牲
第42・44句 上平声十一眞(しん)韻の濱、人
の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城。明治20年福岡市有田に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
