漢詩紹介
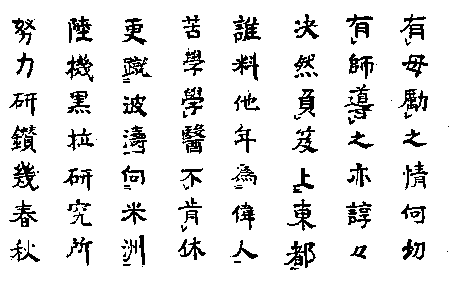
読み方
- 野口英世(6-2)<松口月城>
- 母有り之を勵まして 情何ぞ切なる
- 師有り之を導きて 亦諄諄
- 決然笈を負うて 東都に上る
- 誰か料らん 他年 偉人と爲るを
- 苦學醫を學び 休むことを肯ぜず
- 更に波濤を蹴って 米洲に向こう
- 陸機黒拉 研究所
- 努力研鑽 幾春秋
- のぐちえいせい<まつぐちげつじょう>
- ははありこれをはげまして じょうなんぞせつなる
- しありこれをみちびきて またじゅんじゅん
- けつぜんきゅうをおうて とうとにのぼる
- たれかはからん たねん いじんとなるを
- くがくいをまなび やすむことをがえんぜず
- さらにはとうをけって べいしゅうにむこう
- ロックフェラ けんきゅうしょ
- どりょくけんさん いくしゅんじゅう
字解
-
- 諄 諄
- 繰り返し心をこめる
-
- 負 笈
- 遊学の途に上る 「笈」は書物を入れる竹製の箱
-
- 肯
- 承知する
-
- 陸機黒拉研究所
- ロックフェラー研究所 世界に有名な医学研究所
意解
彼の母は情厚く、不憫(ふびん)な彼を強く励まし、さらに学校の恩師は少年が上級学校へ進むようにと心をこめて導いた。
その励ましを得て遊学する決意を固め上京した。この少年が後年偉大な人物になろうとは誰が予想したであろうか。
都では苦学しながら医学に邁進(まいしん)し、片時も休むことなど思わず、さらに海を渡ってアメリカに向かった。
ロックフェラー研究所では何年にもわたって努力研鑽を積んだ。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、韻は次の通りである。
第2・4句 下平声八庚(こう)韻の平、生
第6・8句 上平声四支(し)韻の資、絲
第10・12句 上平声十一眞(しん)韻の諄、人
第13~16句 下平声十一尤(ゆう)韻の休、洲、秋
第18・20句 去声九泰(たい)韻の會、大
第22・24句 下平声八庚(こう)韻の聲、榮
第26・28句 上平声四支(し)韻の姿、離
第30・32句 下平声八庚(こう)韻の情、聲
第34・36句 入声九屑(せつ)韻の烈、傑
第37~40句 下平声八庚(こう)韻の驚、征、牲
第42・44句 上平声十一眞(しん)韻の濱、人
の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城。明治20年福岡市有田に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
