漢詩紹介
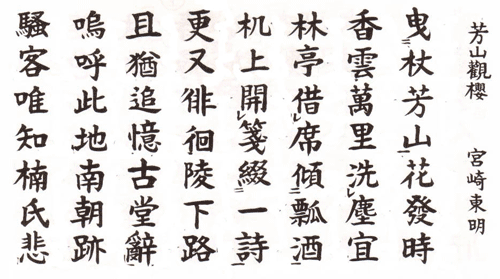
読み方
- 芳山觀櫻<宮崎東明>
- 杖を芳山に曳き 花發く時
- 香雲萬里 塵を洗うに宜し
- 林亭席を借って 瓢酒を傾け
- 机上箋を開いて 一詩を綴る
- 更に又徘徊す 陵下の路
- 且つ猶追憶す 古堂の辭
- 嗚呼此地 南朝の跡
- 騒客唯知る 楠氏の悲しみ
- ほうざんかんおう<みやざきとうめい>
- つえをほうざんにひき はなひらくとき
- こううんばんり ちりをあろうによろし
- りんていさけをかって ひょうしゅをかたむけ
- きじょうせんをひらいて いっしをつづる
- さらにまたはいかいす りょうかのみち
- かつなおついおくす こどうのことば
- ああこのち なんちょうのあと
- そうかくただしる なんしのかなしみ
字解
-
- 香 雲
- 咲き乱れた桜花などの眺めを雲に見立てていう語
-
- 林 亭
- 林の中のあずまや 休憩所として設けた小建物
-
- 瓢 酒
- ひさごに入れた酒
-
- 陵下路
- 天皇の墓のあるあたりの道
-
- 古堂辭
- 如意輪堂にある楠正行(まさつら)が出陣に当たり鏃(やじり)で刻んだ「かえらじとかねて思えば梓弓なき数にいる名をぞとどむる」の辞世の句
-
- 騒 客
- 詩人 ここでは作者自身のこと
意解
桜の花が満開の頃、吉野山を訪ねた。見わたす限り一面に咲いた桜花の眺めは、この世のわずらわしいことをきれいに洗い流してくれるのによい。
林の中のあずまやに場所を借りてひさごの酒を飲み、机の上に紙をひろげ思い浮かぶ詩を書きつけた。
更に後醍醐天皇陵のあたりを散策し、如意輪堂の板壁に刻まれた楠正行公の辞世の句に一層深い思いをめぐらすのであった。
ああ、この地は南北朝時代、後醍醐天皇が朝廷を置かれた場所であったのだ。私は風騒の客として天皇の志もさることながら楠氏の無念を悲しく思うのである。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声四支(し)韻の時、宜、詩、辭、悲の字が使われている。
作者略伝
宮崎東明 1889-1969
名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四条村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日82歳にて没す。
