漢詩紹介
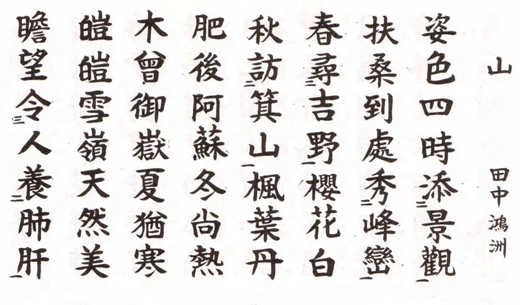
読み方
- 山<田中鴻洲>
- 姿色四時に 景觀を添う
- 扶桑到る處 峰巒秀ず
- 春は吉野を尋ぬれば 櫻花白く
- 秋は箕山を訪えば 楓葉丹し
- 肥後の阿蘇は 冬尚熱く
- 木曾の御嶽は 夏猶寒し
- 皚皚たる雪嶺 天然の美
- 瞻望人をして 肺肝を養わしむ
- やま<たなかこうしゅう>
- ししょくしじに けいかんをそう
- ふそういたるところ ほうらんひいず
- はるはよしのをたずぬれば おうかしろく
- あきはみのおをとえば ふうようあかし
- ひごのあそは ふゆなおあつく
- きそのおんたけは なつなおさむし
- がいがいたるせつれい てんねんのび
- せんぼうひとをして はいかんをやしなわしむ
字解
-
- 四 時
- 四季 春夏秋冬
-
- 扶 桑
- 中国東方にあるという国 日本国の異称
-
- 峰 巒
- 山々 また連なっている山
-
- 箕 山
- 大阪府箕面(みのお)市にある 紅葉の名所として有名
-
- 瞻 望
- はるかにあおぎ見ること 遠く見渡すこと
-
- 肺 肝
- 心の奥底 まごころ
意解
山の姿や形は四季折々に変化してその美しさを添え、日本の到るところに、そうしたすばらしい山々がある。
春、吉野山を尋ねると一面に咲き誇った桜の花が白く広がり、秋、箕面を訪れると楓の葉が真っ赤に紅葉しており、まことに美しい。
肥後の阿蘇山は冬なお熱く、木曽の御嶽山は夏なお寒い。
真っ白な雪をいただいている富士山は自然の美しさであり、それらをはるかに仰ぎ見ることによって美しい日本の四季、そして人々に美しい心を養うよう教えていることを知る。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声十四寒(かん)韻の觀、巒、丹、寒、肝の字が使われている。
作者略伝
田中鴻洲 1911-1995
明治44年12月大阪市港区に生まれる。名は章之(あきゆき)、鴻洲は号。旧制大阪商業学校卒業、その後、泊園書院で漢学を専攻した。作詩は藤澤黄坡(こうは)、宮崎東明等に就き、吟を眞子西洲(まなごさいしゅう)、八木哲洲に師事した。社団法人関西吟詩文化協会総本部副会長として多数の門下を養成する。著書に詩集4巻がある。平成7年6月2日83歳にて没す。
