漢詩紹介
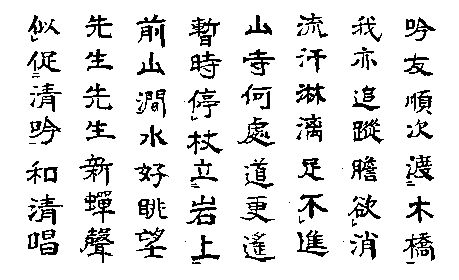
読み方
- 攝津峽吟行(4-2)<宮崎東明>
- 吟友順次 木橋を渡る
- 我も亦追蹤 膽消えんと欲す
- 流汗淋漓 足進まず
- 山寺は何處ぞ 道更に遙かなり
- 暫時杖を停めて 岩上に立つ
- 前山澗水 好眺望
- 先生先生 新蝉の聲
- 清吟を促すに似て 和して清唱
- せっつきょうぎんこう<みやざきとうめい>
- ぎんゆうじゅんじ もっきょうをわたる
- われもまたついしょう たんきえんとほっす
- りゅうかんりんり あしすすまず
- さんじはいずこぞ みちさらにはるかなり
- ざんじつえをとどめて がんじょうにたつ
- ぜんざんかんすい こうちょうぼう
- せんせいせんせい しんぜんのこえ
- せいぎんをうながすににて わしてせいしょう
字解
-
- 膽欲消
- 肝をつぶす
-
- 淋 漓
- 汗などがしたたり落ちるさま
-
- 澗 水
- 谷川の水
意解
吟友は順をおって木橋を渡り、私もこれに続いたが肝をつぶすようだ。
そのうち汗がしたたり流れ出てきて、足も進まず、山寺はどこかと見渡すと、まだまだ遠いようだ。
しばらく歩くのをやめて岩の上に立ち止まると、前の山や谷川はとても良い眺めである。
折から若い蝉の声が「センセイセンセイ」と鳴いているように聞こえてくる。それはちょうど私達に清吟を促しているようで、私達も声を合わせて吟じた。
備考
この詩は高槻市の摂津耶馬渓といわれる景勝を朋友と共に吟行をしたときの作である。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第1~4句 上平声十三元(げん)韻の村、魂、繁
第5~8句 去声七遇(ぐう)韻の路、趣、布
第9~12句 下平声二蕭(しょう)韻の橋、消、遙
第13~16句 去声二十三漾(よう)韻の上、望、唱
第17~20句 下平声七陽(よう)韻の央、光、涼
第21~24句 上声十三阮(げん)韻の坂、遠、蹇
第25~32句 上平声十三元(げん)韻の孫、煩、樽、翻、元、源
の字が使われている。
作者略伝
宮崎東明 1889-1969
名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四條村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日没す。年82。
参考
摂津峡
高槻市にあり、淀川支流の芥(あくた)川の中流にある渓谷で奇巌、滝、淵等が多く四季を通じて、桜、新緑、紅葉等の景勝地で、摂津耶馬渓ともいわれる。延長約2キロメートル。
