漢詩紹介
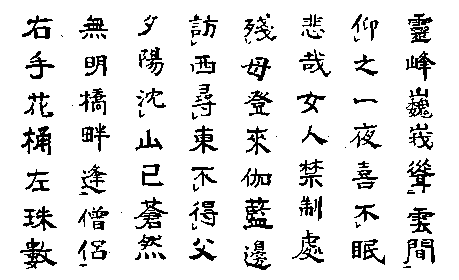
読み方
- 石童丸(3-2)<松口月城>
- 靈峰巍峩として 雲間に聳ゆ
- 之を仰いで一夜 喜び眠らず
- 悲しいかな女人 禁制の處
- 母を殘して登り來る 伽藍の邉
- 西を訪れ東を尋ねて 父を得ず
- 夕陽山に沈んで 已に蒼然
- 無明の橋畔 僧侶に逢う
- 右手に花桶 左に珠數
- いしどうまる<まつぐちげつじょう>
- れいほうぎがとして うんかんにそびゆ
- これをあおいでいちや よろこびねむらず
- かなしいかなにょにん きんせいのところ
- ははをのこしてのぼりきたる がらんのほとり
- にしをおとずれひがしをたずねて ちちをえず
- せきようやまにしずんで すでにそうぜん
- むみょうのきょうはん そうりょにあう
- めてにはなおけ ひだりにじゅず
付記
八木哲洲宗師範曰く「この詩を吟詠する時、行基菩薩のよまれた古歌の一首をいれ朗詠すれば、一層哀調を帯びて一段と吟詠効果あり」と。
夕陽沈山已蒼然
ほろほろと 鳴く山鳥の 声きけば
父かとぞ思う 母かとぞ思う
無明橋畔逢僧侶
字解
-
- 靈 峰
- 神聖な山
-
- 巍 峩
- 山の高くそびえるさま
-
- 伽 藍
- 仏道を修行する所 寺
-
- 蒼 然
- 夕暮れの薄暗いさま
-
- 無 明
- 周囲が薄暗いさま
意解
雲間に高く聳える霊峰を仰ぎ見て、明日は父に会える、夫に会えるという喜びに一晩中眠る事も出来ない。
(ところが一夜明けて母子共に山に登ろうとしたところ)ここからは女人禁制で母は登ることが出来ない。やむなく石童丸は母を残して一人で登り伽藍のあたりにたどりついた。
西を訪れ東を尋ねて探せども父なる人に会えず、夕陽が山の向こうに沈みはじめ、あたりは薄暗くなってきた。
薄暗い橋の辺りをさまよっているうちにふと一人の僧侶に出会った。右手には花桶をさげ左手には珠数をもっていた。
備考
この詩は、作者が下記のような石童丸の物語にもとづいて作られた詩である。
詩の構造は古詩の形であって韻は次の通りである。
第2・4句 上平声十五刪(さん)韻の關、山
第6句 去声八霽(せい)韻の歳
第8句 去声十一隊(たい)韻の愛
第10~14句 下平声一先(せん)韻の眠、邊、然
第16~20句 上声七麌(ぐ)韻の數、父、腑
第22・24句 上平声五微(び)韻の衣、飛
の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城。明治20年福岡市有田に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
参考
石童丸の物語
石童丸の物語は、高野山の苅萱堂縁起、長野市安楽山往生寺の縁起や謡曲、浄瑠璃などにより広く世間に流布している。
崇徳(すとく)天皇の時代(1123-41)筑前の守護職加藤兵衛尉繁昌(ひょうえのじょうしげまさ)は、香椎(かしい)の宮に世嗣出産の願をかけ男児を得たのが繁氏である。繁氏17歳の時家臣原田種正の娘桂子を妻とした。19歳のときに父を失う。
繁氏は仁平(にんぺい)元年(1151)花見の帰途雨に遭い、朽木尚光(くちきなおみつ)の家に雨宿りをし、その縁で娘千里(ちさと)を妾としたが、本妻桂子の嫉妬はげしく千里を亡きものにしようとした。繁氏は人の世の憂きことを嘆き、俗世を離れ仏門に入るべく高野山に登り、覚心上人によって得度(とくど)し苅萱道心と名乗った。国の千里は繁氏の後を追ったが、播磨国太山寺(はりまのくにだいさんじ=現在の神戸市西区)に身を寄せ、石童丸を生み14年間そこに滞在した。
石童丸14歳の時、父繁氏が出家して高野山にいるとの話を伝え聞き、母と一緒に高野山をたずねたが女人禁制で母は登れずやむなく一人で登り苅萱道心にあう。しかし父は一度恩愛のきずなを断ち出家した身であり、親を名乗らず子を帰らせる。石童丸は麓の宿に帰る。永万(えいまん)元年(1165)母は病のために死ぬ。
石童丸は再び山に登り母の死を伝える。父は出家の身である事を考え、石童丸を弟子として信生法師と名乗らせ、生涯父子を名乗らず念仏修行の生活を送ったといわれる。
