漢詩紹介
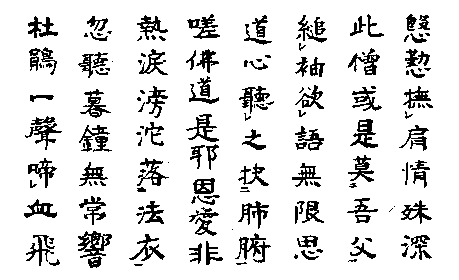
読み方
- 石童丸(3-3)<松口月城>
- 慇懃肩を撫でて 情殊に深し
- 此の僧或いは是 吾が父なる莫からんか
- 袖に縋りて語らんと欲す 無限の思い
- 道心之を聽いて 肺腑を抉らる
- 嗟佛道是か 恩愛非か
- 熱涙滂沱として 法衣に落つ
- 忽ち聽く暮鐘 無常の響き
- 杜鵑一聲 血に啼いて飛ぶ
- いしどうまる<まつぐちげつじょう>
- いんぎんかたをなでて じょうことにふかし
- このそうあるいはこれ わがちちなるなからんか
- そでにすがりてかたらんとほっす むげんのおもい
- どうしんこれをきいて はいふをえぐらる
- ああぶつどうぜか おんあいひか
- ねつるいぼうだとして ほういにおつ
- たちまちきくぼしょう むじょうのひびき
- とけんいっせい ちにないてとぶ
字解
-
- 慇 懃
- ねんごろに
-
- 肺 腑
- はらわた 心の奥底
-
- 滂 沱
- 涙がさかんに流れるさま
意解
僧侶はねんごろに石童丸の肩を撫で親切に慰めてくれた。もしかするとこの僧侶こそが探し求めている父ではあるまいか。
石童丸は法衣の袖にすがり身の上話をすると、繁氏はこの子が千里(ちさと)の生んだわが子であったのかと万感胸に迫り腸(はらわた)を抉られる思いがした。
ああ、何とあわれなわが子よ。仏道に帰依(きえ)するものとしてこのまま帰すのが正しい道か、父と名乗って血縁の恩愛にすがるのは間違いなのか。とめどなく涙が流れ法衣が濡れるばかりである。
折しも寺の夕暮れの鐘が無常に鳴り響き、ホトトギスが血を吐くように鳴き渡った。
備考
この詩は、作者が下記のような石童丸の物語にもとづいて作られた詩である。
詩の構造は古詩の形であって韻は次の通りである。
第2・4句 上平声十五刪(さん)韻の關、山
第6句 去声八霽(せい)韻の歳
第8句 去声十一隊(たい)韻の愛
第10~14句 下平声一先(せん)韻の眠、邊、然
第16~20句 上声七麌(ぐ)韻の數、父、腑
第22・24句 上平声五微(び)韻の衣、飛
の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城。明治20年福岡市有田に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
参考
石童丸の物語
石童丸の物語は、高野山の苅萱堂縁起、長野市安楽山往生寺の縁起や謡曲、浄瑠璃などにより広く世間に流布している。
崇徳(すとく)天皇の時代(1123-41)筑前の守護職加藤兵衛尉繁昌(ひょうえのじょうしげまさ)は、香椎(かしい)の宮に世嗣出産の願をかけ男児を得たのが繁氏である。繁氏17歳の時家臣原田種正の娘桂子を妻とした。19歳のときに父を失う。
繁氏は仁平(にんぺい)元年(1151)花見の帰途雨に遭い、朽木尚光(くちきなおみつ)の家に雨宿りをし、その縁で娘千里(ちさと)を妾としたが、本妻桂子の嫉妬はげしく千里を亡きものにしようとした。繁氏は人の世の憂きことを嘆き、俗世を離れ仏門に入るべく高野山に登り、覚心上人によって得度(とくど)し苅萱道心と名乗った。国の千里は繁氏の後を追ったが、播磨国太山寺(はりまのくにだいさんじ=現在の神戸市西区)に身を寄せ、石童丸を生み14年間そこに滞在した。
石童丸14歳の時、父繁氏が出家して高野山にいるとの話を伝え聞き、母と一緒に高野山をたずねたが女人禁制で母は登れずやむなく一人で登り苅萱道心にあう。しかし父は一度恩愛のきずなを断ち出家した身であり、親を名乗らず子を帰らせる。石童丸は麓の宿に帰る。永万(えいまん)元年(1165)母は病のために死ぬ。
石童丸は再び山に登り母の死を伝える。父は出家の身である事を考え、石童丸を弟子として信生法師と名乗らせ、生涯父子を名乗らず念仏修行の生活を送ったといわれる。
