漢詩紹介
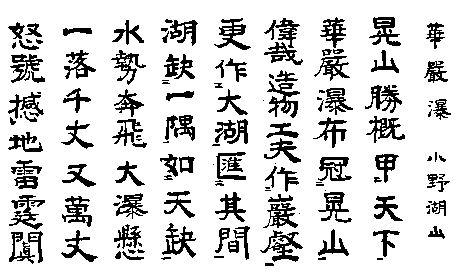
読み方
- 華嚴の瀑(3-1)<小野湖山>
- 晃山の勝概は 天下に甲たり
- 華嚴の瀑布は 晃山に冠たり
- 偉なるかな造物の工夫 嚴壑を作り
- 更に大湖を作り 其の間に匯らす
- 湖の一隅の缺けること 天の缺けたるが如く
- 水勢奔飛して 大瀑懸かる
- 一落千丈 又萬丈
- 怒號地を撼かして 雷霆闐たり
- けごんのたき<おのこざん>
- こうざんのしょうがいは てんかにこうたり
- けごんのばくふは こうざんにかんたり
- いなるかなぞうぶつのくふう がんがくをつくり
- さらにたいこをつくり そのあいだにめぐらす
- このいちぐうのかけること てんのかけたるがごとく
- すいせいほんぴして たいばくかかる
- いちらくせんじょう またばんじょう
- どごうちをうごかして らいていてんたり
字解
-
- 晃 山
- 日光山
-
- 勝 概
- 景色がよい
-
- 甲
- 物事の第一
-
- 冠
- 首位
-
- 造 物
- 万物を作った神
-
- 嚴 壑
- 岩と谷
-
- 匯
- 水をたたえる
-
- 雷 霆
- 急に鳴る雷
-
- 闐
- 雷鳴が盛んなようす
意解
日光山の景色がよいことは天下第一であり、華厳の瀑布はその日光の中でも首位である。
万物を創造した神々の工夫はなんと偉大なもので、ここに大きな岩や谷をお作りになり、その間に大きな湖を配置された。
この湖の一隅が欠けているのはちょうど天の一方が欠けているようなもので、そこから水が勢いよくはしり落ちて大瀑布となっている。
しかもそれは千丈あるいは万丈の高さから落下し、怒り叫ぶ響きは地を揺り動かし、また雷が盛んに鳴るようでもある。
備考
この詩の構造は古詩の形であって韻は次の通りである。
第2・4・20句 上平声十五刪(さん)韻の山、間、顔
第6・8・10・16・23句 下平声一先(せん)韻の懸、闐、烟、千、然
第12・18句 上平声十四寒(かん)韻の寒、觀
第14句 下平声十二侵(しん)韻の今
の字が通韻して使われている。
参考
一韻到底格 近体詩では、決められた句末に同じ韻を使う事になっている。これを一韻到底格という。
換 韻 これに対し古詩では数句ごとに途中で韻を変えることが出来る。これを換韻という。
作者略伝
小野湖山 1814-1910
江戸時代後期、明治の漢詩人。近江(滋賀県)東浅井郡田根村で医師の横山玄篤(げんとく)の長男として生まれる。医学を学び、梁川星巖の玉池(ぎょくち)吟社に入って詩を学んだ。本姓は横山、名は長愿(ながよし)、また巻(おさむ)ともいう。湖山は号。勤王の志士と交わり明治維新後は一時新政府に仕えたこともある。大阪で優遊吟社をおこし子弟を教えた。のち東京に移住し明治43年3月病のため没す。年97。著書に「湖山楼詩鈔」「湖山近稿」「湖山消閑集」などがある。
