漢詩紹介
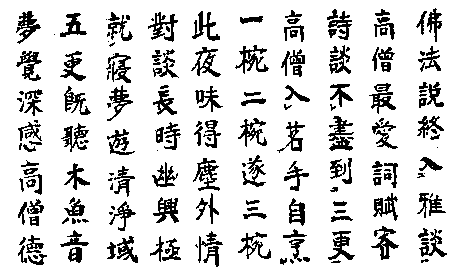
読み方
- 山寺に宿る(2-2)<宮崎東明>
- 佛法説き終わって 雅談に入り
- 高僧最も愛す 詞賦の客
- 詩談盡きず 三更に到り
- 高僧茗を入れて 手自ら烹る
- 一椀二椀 遂に三椀
- 此の夜味わい得たり 塵外の情
- 對談長時 幽興の極
- 寢に就いて夢は遊ぶ 清浄の域
- 五更既に聽く 木魚の音
- 夢覺めて深く感ず 高僧の德
- さんじにやどる<みやざきとうめい>
- ぶっぽうときおわって がだんにいり
- こうそうもっともあいす しぶのかく
- しだんつきず さんこうにいたり
- こうそうめいをいれて てみずからにる
- いちわんにわん ついにさんわん
- このよあじわいえたり じんがいのじょう
- たいだんちょうじ ゆうきょうのきょく
- しんについてゆめはあそぶ しょうじょうのいき
- ごこうすでにきく もくぎょのおと
- ゆめさめてふかくかんず こうそうのとく
字解
-
- 雅 談
- 風雅な談話 上品な談話
-
- 詞賦客
- 詩をつくる人
-
- 茗
- お茶
-
- 塵外情
- 世間を離れた気持ち
-
- 幽興極
- 静かな趣がこの上ないこと
-
- 清浄域
- 清くてけがれのない 邪念のない
意解
仏の教えを説いていただいたのち、風流な世間話となったが、高僧は私を詩人の客として大変好感をもって接してくれた。
詩の話はつきることなく、夜中の12時ごろになり、高僧自らお茶を入れてくださった。
この夜、一椀二椀三椀とお茶をいただくうちに、世俗を離れたすがすがしい気分を味わうことができた。
楽しい語らいは長時間つづき、この上なく静かな趣で床に就いたが、夢の中でも清らかな世界に遊んだ。
午前4時ごろ既に木魚の音が聞こえてきて夢から覚め、高僧の徳の高いことを一層深く感じた。
備考
この詩は人里離れた山深い処に建つ古い寺を尋ねて一夜の宿を乞い、高徳の住僧と深夜まで風流雅談に時の移るのを忘れ、俗世を離れて仙境に遊んだ心情を賦している。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第1・2・4句 去声二十六宥(ゆう)韻の痩、柚、透
第5・6・8句 上平声二冬(とう)韻の封、鐘、逢
第9・10・12句 入声十一陌(はく)韻の席、白、客
第13・14・16句 下平声八庚(こう)韻の更、烹、情
第17・18・20句 入声十三職(しょく)韻の極、域、德
の字が使われている。
作者略伝
宮崎東明 1889-1969
名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四條村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日没す。年82。
