漢詩紹介
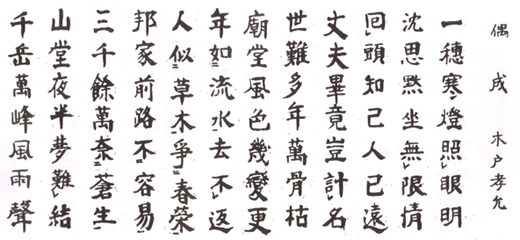
読み方
- 偶成<木戸孝允>
- 一穗の寒燈 眼を照らして明らかなり
- 沈思默坐 限り無きの情
- 頭を囘らせば 知己の人 已に遠し
- 丈夫畢竟 豈名を計らんや
- 世難多年 萬骨枯れ
- 廟堂の風色 幾變更
- 年は流水の如く 去って返らず
- 人は草木に似て 春榮を争う
- 邦家の前路 容易ならず
- 三千餘萬 蒼生を奈んせん
- 山堂夜半 夢結び難く
- 千岳萬峰 風雨の聲
- ぐうせい<きどこういん>
- いっすいのかんとう まなこをてらしてあきらかなり
- ちんしもくざ かぎりなきのじょう
- こうべをめぐらせば ちきのひと すでにとおし
- じょうふひっきょう あになをはからんや
- せなんたねん ばんこつかれ
- びょうどうのふうしょく いくへんこう
- としはりゅうすいのごとく さってかえらず
- ひとはそうもくににて しゅんえいをあらそう
- ほうかのぜんろ よういならず
- さんぜんよまん そうせいをいかんせん
- さんどうやはん ゆめむすびがたく
- せんがくばんぽう ふううのこえ
字解
-
- 一穗寒燈
- 一すじのさびしげな灯火 灯火が稲の穂先のような形に見えるのでいう
-
- 豈計名
- 「豈」は反語 どうして名誉を得ようなどと努めようか いや努めない
-
- 世 難
- 維新前後の世の乱れ
-
- 萬骨枯
- 多くの志士たちが死んだこと 唐の曹松の「己亥歳」の詩に「一将功成万骨枯」とあるにもとづく
-
- 廟 堂
- 廟堂は朝廷 ここでは明治新政府
-
- 風 色
- 物の様子 ここでは維新成立後の権力争いでみだれた様子
-
- 蒼 生
- 草があおあおと生ずることから人民の多いことにたとえる
-
- 春 榮
- 自分の利益をはかり出世を願う 私利私欲を追う
意解
ひとすじのさびしげな灯火があかあかと自分の眼を照らしている中で、黙座して深い思いにふけっていると、つぎつぎと無限の感慨がわいてくる。
かえりみれば、幕末維新に国事に奔走した親友たちは既にこの世にいなく、彼らのような立派な男子は、ひたすら国家のために身を犠牲にしたのであって、つまるところ一身の名誉をはかったためではない。
多年にわたる動乱のために多くの志士たちは、その尊い命を失い、維新後の政府もめまぐるしい勢力争いで、幾度もその様子を変えた。
こうして過ぎ去った歳月は流れる水のごとく二度と返ってこない。人々は草木が春の美しさを競うように、私利私欲のみを追っている。
国家の前途はまだまだ容易ならざるものがあるのに、三千余万もの国民をいったいどうしたものであろうか。
静かな山荘の夜中、心配で寝つかれないでいると、周辺の多くの峰々には風雨の音が鳴りひびいている。
備考
この詩は、作者が痔を患い、箱根で療養していた当時、憂国の情を吐露したものである。
詩の構造は、下平声八庚(こう)韻の明、情、名、更、榮、生、聲の字が使われており「一韻到底格」の詩である。
作者略伝
木戸孝允 1833-1877
徳川末期から明治初期頃の武士で政治家。明治維新の元勲。天保4年6月、長州(山口県)萩の城下、藩医和田昌景の長男として生まれる。幼時、桂九郎兵衛の養子となり桂小五郎の呼名で知られる。のち藩主の命により木戸準一郎と改称、明治2年孝允と改める。松菊はその号。吉田松陰門下で明治維新に活躍し廟堂の要職にあり維新の三傑(大久保利通・西郷隆盛・木戸孝允)といわれる。明治10年5月没。年45。
