漢詩紹介
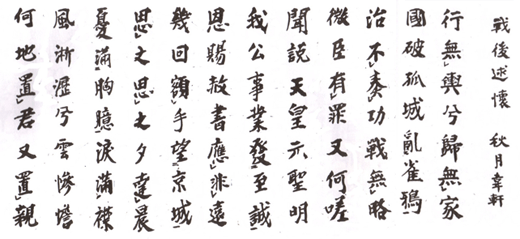
読み方
- 戰後述懷<秋月韋軒>
- 行くに輿無く 歸るに家無し
- 國破れて孤城 雀鴉亂る
- 治に功を奏せず 戰いに略無し
- 微臣罪有り 又何をか嗟かん
- 聞く説く天皇 元聖明
- 我が公の事業 至誠に發す
- 恩賜の赦書 應に遠きに非ざるべし
- 幾回か手を額にして 京城を望む
- 之を思い之を思うて 夕べより晨に達す
- 憂いは胸臆に滿ちて 涙襟に滿つ
- 風は淅瀝として 雲は慘憺
- 何れの地にか君を置き 又親を置かん
- せんごじゅっかい<あきづきいけん>
- ゆくにこしなく かえるにいえなし
- くにやぶれてこじょう じゃくあみだる
- ちにこうをそうせず たたかいにりゃくなし
- びしんつみあり またなにをかなげかん
- きくならくてんのう もとせいめい
- わがこうのじぎょう しせいにはっす
- おんしのしゃしょ まさにとおきにあらざるべし
- いくたびかてをひたいにして けいじょうをのぞむ
- これをおもいこれをおもうて ゆうべよりあしたにたっす
- うれいはきょうおくにみちて なみだきんにみつ
- かぜはせきれきとして くもはさんたん
- いずれのちにかきみをおき またおやをおかん
字解
-
- 輿
- かご 乗り物
-
- 孤 城
- ここでは会津若松城 鶴ヶ城
-
- 微 臣
- 家臣の謙遜語 作者自身
-
- 聖 明
- すぐれた 聡明
-
- 我 公
- 我らの藩主 松平容保(かたもり)
-
- 胸 臆
- 胸のうち
-
- 淅 瀝
- 雨雪風などの寂しい音のさま
-
- 慘 憺
- ひどくうす暗いさま
意解
会津戦争に敗れ、藩士とその家族たちは出て行くにも乗り物がなく帰るにも家がない。会津の国は敗れ孤立した鶴ヶ城にはただ雀鴉が乱れさわいでいるばかりである。
政治には功なく、戦争にも秀でた戦略もなく、亡国の罪は我等家臣にあり今更嘆いてもどうにもならない。
聞くところによれば、天皇は立派で聡明なおかたであられるから我が藩公の企てた事業は、天皇に対する至誠から発したものであることをお察しくださるだろう。
遠からず恩赦が下されるであろうと、幾度も手を合わせ京都の方を望んでまちわびているのである。
あれこれ思うと夜通し眠れなく、心配が胸一杯で涙は襟に満ちて乾くひまもない。
折から、秋も深まり吹く風も寂しく雲もひどく薄暗く、何処へどうしたら君と親とを安らかにおくことが出来るのであろうか。
備考
この詩は、戊辰(ぼしん)戦争による会津若松藩の末路の悲惨さを、作者自身臣下の一人としてその心境を吐露 した哀話詩である。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第一・二・四句 下平声六麻(ま)韻の家、鴉、嗟
第五・六・八句 下平声八庚(こう)韻の明、誠、城
第九・十二句 下平声十一眞(しん)韻の晨、親
第十句 下平声十二侵(しん)韻の襟
の字が使われている。
作者略伝
秋月韋軒 1824-1900
会津藩士、明治の漢学者。名は悌二郎、韋軒は号。天保13年(1842)江戸に上り、弘化3年(1846)昌平黌に入る。後、藩主松平容保が守護職として京都に上るや、韋軒もこれに従い助ける。明治元年鳥羽伏見の戦いが起こり、敗れて江戸に下り、後、会津若松城に入って、落城後、終身禁固に処せられたが、明治5年、特赦により一時新政府に仕える。のち一高、五高に奉職する。明治33年(1900)没。年76。
