漢詩紹介
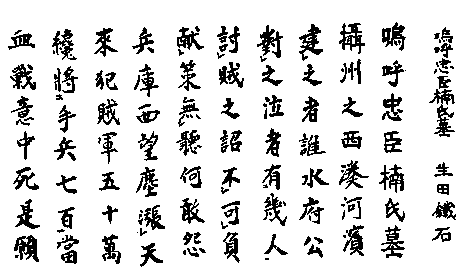
読み方
- 嗚呼忠臣楠氏の墓(2-1)<生田鐡石>
- 嗚呼忠臣 楠氏の墓
- 攝州の西 湊河の濱
- 之を建る者は誰ぞ 水府公
- 之に對して泣く者は 幾人有りや
- 賊を討ての詔は 負く可からず
- 策を獻じて聽かるる無きも 何ぞ敢て怨みん
- 兵庫西に望めば 塵天に漲る
- 來り犯す賊軍 五十萬
- 纔かに手兵 七百を將って當たる
- 血戰意中 死を是願う
- ああちゅうしんなんしのはか<いくたてっせき>
- ああちゅうしん なんしのはか
- せっしゅうのにし みなとがわのほとり
- これをたつるものはたれぞ すいふこう
- これにたいしてなくものは いくにんありや
- ぞくをうてのみことのりは そむくべからず
- さくをけんじてきかるるなきも なんぞあえてうらみん
- ひょうごにしにのぞめば ちりてんにみなぎる
- きたりおかすぞくぐん ごじゅうまん
- わずかにしゅへい しちひゃくをもってあたる
- けっせんいちゅう しをこれねごう
字解
-
- 攝 州
- 現在の大阪府北部から兵庫県東部の総称
-
- 水府公
- 水戸の徳川光圀
-
- 塵漲天
- 「塵」は逆賊である足利軍 その大軍が天地を覆うように迫り来る
意解
「嗚呼忠臣楠氏墓」というのが摂津の国の西、つまり湊川のほとりに建立されている。
これを建てた人は誰であろうか。それはあの水府公、即ち水戸光圀公であり、以来この墓と対面して涙を流した人は一体幾人いただろうか、いや数え切れないほどいただろう。
逆賊である足利軍を討伐せよとの後醍醐天皇のご命令を戴き、勝ち目のない戦だと知りつつ、背くことはできなくて、次善の策略を申しあげたものの、お聞き届けにならなかった。それでも正成は決して帝をお怨みすることはなかった。
西の方兵庫を眺めると塵を捲きあげて賊軍50万の大軍が天地を覆うように迫って来た。
それに対し南朝軍はわずかに手持ちの兵700余騎で対抗し、血を見る負け戦にもかかわらず、兵士たちは潔い戦死を覚悟する者ばかりであった。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、韻は次の通りである。
第2・4句 上平声十一眞(しん)韻の濱、人
第6・8・10・12句 去声十四願(がん)韻の怨、萬、願、獻
第14・16句 上平声十三元(げん)韻の尊、存
第18・20句 去声七遇(ぐう)韻の訴、墓
の字が使われている。
作者略伝
生田鐡石 ?-1933
山口県出身、陸軍軍人(中佐)。名は清範(きよのり)、鉄石は号。古詩に長じていると言われ詩文も平易明快である。熊本に永住し昭和8年没。
参考
湊川神社
神戸市中央区多聞通3-1にある。
