漢詩紹介
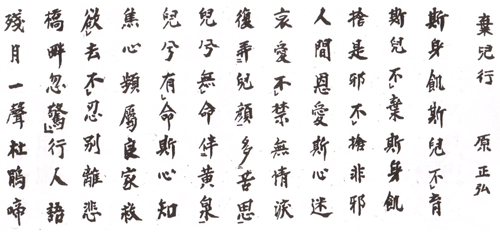
読み方
- 棄兒行<原正弘>
- 斯の身飢ゆれば 斯の兒育たず
- 斯の兒棄てざれば 斯の身飢ゆ
- 捨つるが是か 捨てざるが非か
- 人間の恩愛 斯の心に迷う
- 哀愛禁ぜず 無情の涙
- 復兒顔を弄して 苦思多し
- 兒や命無くんば 黄泉に伴わん
- 兒や命有らば 斯の心を知れ
- 焦心頻りに屬す 良家の救いを
- 去らんと欲して忍びず 別離の悲しみ
- 橋畔忽ち驚く 行人の語るを
- 殘月一聲 杜鵑啼く
- きじこう<はらまさひろ>
- このみうゆれば このこそだたず
- このこすてざれば このみうゆ
- すつるがぜか すてざるがひか
- にんげんのおんあい このこころにまよう
- あいあいきんぜず むじょうのなみだ
- またじがんをろうして くしおおし
- じやめいなくんば こうせんにともなわん
- じやめいあらば このこころをしれ
- しょうしんしきりにしょくす りょうかのすくいを
- さらんとほっしてしのびず べつりのかなしみ
- きょうはんたちまちおどろく こうじんのかたるを
- ざんげついっせい とけんなく
字解
-
- 棄兒行
- 「行」は詩体のひとつ ここでは棄て児の詩
-
- 不捨非邪
- 捨てないのが悪いのか この表現では直前の語と同意となるので王長春の「和詩選」には「非」を「是」としている
-
- 弄
- もてあそぶ ここではほお擦りしてあやす
-
- 命
- 運命
-
- 黄 泉
- あの世 冥土
-
- 兮
- 置き字だから読まない
-
- 焦 心
- あせり いらだち
-
- 屬
- 嘱に同じ 切望する
-
- 橋 畔
- 橋のたもと
意解
この身が飢えるとこの児は育たないし、この児を棄てなければ、自分もまた飢える。
捨てるのがよいのか、捨てないのが悪いのか、人としての父子の情愛に心は千々に乱れる。
哀しさ、いとおしさのために無情の涙が溢れ出て、止めようもなく、幾たびとなく我が児にほお擦りし、その無心の姿に、せつない思いは胸に詰まる。
(意を決して今お前を棄てようとするのであるが)我が児よ、もし運命がなかったら、あの世に道連れにしよう。もし運命がお前に味方し、生きながらえるなら、親としてのこの切ない心を知ってほしい。
私の焦る心は、良家の救いの手が差し伸べられることをひたすら願うばかりで、(さて置き去りにしようとしてみたものの)別離の悲しみが溢れ、とても立ち去ることはできない。
折しも、通行人の話し声が近づいてくるのにはっと驚き、ついにその児を捨てて立ち去ってゆくと、夜明けの空には、この哀しいありさまを残月が照らし、血を吐くようにホトトギスが一声鳴いて渡っていった。
備考
この詩は作者の友人がある日、隅田川吾妻橋のたもとで棄て子のあるのを見て、わが子を棄てなければならない親の境遇に同情したのを聞き、友人に代って作ったものである。
この詩は世に雲井龍雄の作と伝えられているが、雲井龍雄全集の編者曰く「原正弘の作る所にて龍雄の作に非ず。なお山田済斎先生編の養気集も亦 原正弘の作と為す」とある。
詩の構造は七言古詩の形であって、韻は次の通りである。
第二・六・八・十句 上平声四支(し)韻の飢、思、知、悲
第四・十二句 上平声八斉(せい)韻の迷、啼
の字が使われている。
作者略伝
原 正弘 生没年不明
山形県米沢の人。江戸末期の人。
