詩歌紹介
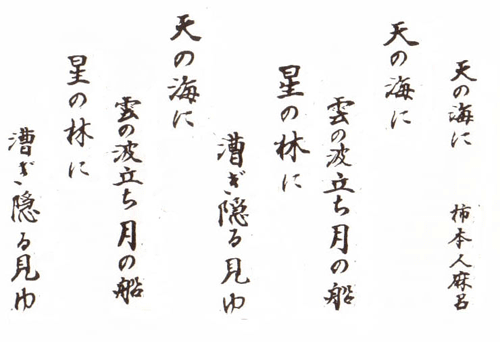
吟者:熊谷 峰龍
2010年9月掲載
読み方
- 天の海に<柿本人麻呂>
- 天の海に 雲の波立ち 月の船
- 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ
- あめのみに<かきのもとのひとまろ>
- あめのみに くものなみたち つきのふね
- ほしのはやしに こぎかくるみゆ
語意
-
- 天の海に
- 大海にも似た大空よ
-
- 雲の波立ち
- 揺れ動く波のように空に雲がかかって
-
- 月の船
- 船の形に似た三日月
-
- 星の林
- 天上に張り巡る無数の星
歌意
大空の海に雲の波がたって、月の船が、きらめく星の林の中に漕ぎ隠れてゆく。
出典
「萬葉集」(巻七)1068
作者略伝
柿本人麻呂 生没年不詳
万葉歌人。持統(じとう)・文武(もんむ)両天皇に仕えた宮廷歌人という。雄大荘重な長歌の形式を完成する一方、短歌においても抒情詩人として高い成熟度を示し、万葉歌人の中の第一人者とされる。
伝記は明らかではないが、和銅(708-715)の初め頃、50歳ぐらいで任地、石見国(いわみのくに)で死んだという。後世、歌聖と仰がれた。「柿本人麻呂歌集」がある。
備考
柿本人麻呂は、文武天皇がまだ10歳の軽皇子(かるのみこ)の時代、狩猟に従って阿騎野で有名な「東の野にかぎろひの立つみえてかへりみすれば月傾(かたぶ)きぬ」の歌を詠んだころ、すでに幼い皇子の補佐役的な存在であったと思われる。下記の文武天皇作の漢詩は、人麻 呂の「天の海」の和歌に雰囲気がよく似ているので掲げたものであるが、当時の二人の関係から考えて「詠月」の詩は人麻呂の影響力が及んでいると思われる。
詠 月 文武天皇
月舟移霧渚 げっしゅうむしょにうつり
楓<楫に弋>泛霞濱 ふうしゅうかひんにうかぶ
臺上澄流耀 たいじょうりゅうようにすみ
酒中沈去輪 しゅちゅうきょりんにしずむ
水下斜陰碎 みずくだりてしゃいんくだけ
樹落秋光新 じゅおちてしゅうこうあらたなり
獨以星間鏡 ひとりせいかんのかがみをもって
還浮雲漢津 かえってうんかんのわたしにうかばん
