詩歌紹介
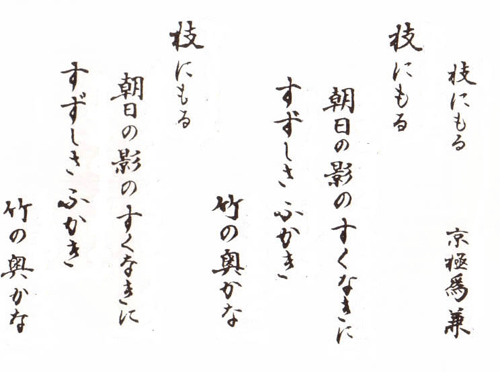
吟者:新子 紅秋
2010年9月掲載
読み方
- 枝にもる<京極為兼>
- 枝にもる 朝日の影の すくなきに
- すずしさふかき 竹の奥かな
- えだにもる<きょうごくためかね>
- えだにもる あさひのかげの すくなきに
- すずしさふかき たけのおくかな
語意
-
- 枝にもる
- 枝にいっぱいの笹葉が茂っているさま
-
- ふかき
- 前の語状況(すずしさ)をより以上に感じさせる語
歌意
竹の林が茂っているため、そこへ射しこむ朝日のひかりが少ない。それだけに、その奥の涼気がいっそうすがすがしく感じられるのである。
出典
「玉葉集」(巻三)夏・419
作者略伝
京極為兼 1254-1332
建長6年-元弘2年。鎌倉後期の歌人。為教(ためのり)の子。本姓藤原。号毘沙門堂(びしゃもんどう)。
持明院統の伏見上皇に信任されて「玉葉集(ぎょくようしゅう)」を撰集。「萬葉集」を重んじ清新奔放な歌風で、保守的な二条家と対立した。
南北朝の政争にかかわり、佐渡、のち土佐に配流(はいる)された。最後には罪を許されたが、都には入れず晩年は和泉に移りその地で没した。年78。歌論書「為兼卿和歌抄」がある。
備考
正二位・大納言を賜わった時期、いとこの二条為世(ためよ)の伝統的歌風と対立。「心の起るにしたがいて」詠歌せよと主張し 、清新な趣をたたえた新しい歌風をうちたてた。
特に自然詠にすぐれ、この歌も彼の信念がよく表現された一首といえよう。
