詩歌紹介
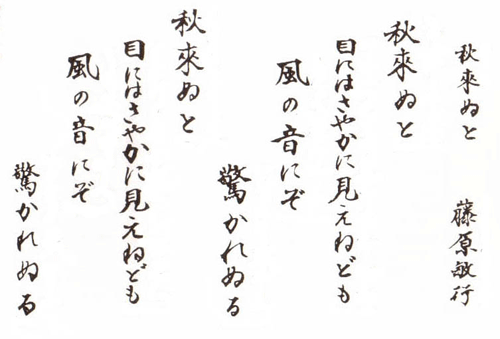
吟者:中谷 淞苑
2011年1月掲載
読み方
- 秋来ぬと<藤原敏行>
- 秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども
- 風の音にぞ 驚かれぬる
- あききぬと<ふじわらのとしゆき>
- あききぬと めにはさやかに みえねども
- かぜのおとにぞ おどろかれぬる
語意
-
- 秋来ぬと
- 秋が来たと
-
- さやかに
- (視覚的に)はっきりと 明瞭
-
- ども
- 接続助詞「ど」に係助詞「も」のついたもの 逆接の確定条件を表す ……けれども ……のに ……だが
-
- おどろかれぬる
- 「おどろく」は気づく 感じとる 「れ」は自発の助動詞「る」の連用形で 自然にはっと気づかされる
歌意
秋が来たと、そのすがたが目の方には、はっきりと見えないけれども、耳の方に聞くさわやかな風の音に、それと知らされたことだ。
出典
「古今和歌集」(巻四)秋歌上・169
作者略伝
藤原敏行 ?-901頃
平安時代初期の歌人。三十六歌仙の一人。父は陸奥出羽(むつでわ)、按察使(あぜち)藤原富士麿(ふじまろ)。母は刑部卿紀名虎(ぎょうぶきょうきのなとら)の女(むすめ)。従四位・右兵衛督に至る。能書家としても知られ、少内記を勤めた。後世空海と並称された。
歌集に「敏行集」がある。また「古今和歌集」以下の勅撰集に29首入集する。
「神護寺鐘銘」「江談抄」「日本紀略」などの能書あり。
備考
この歌の前書きに「秋立つ日詠める」とある。つまり立秋の日に、鋭くも聴覚をとおして秋の訪れを知ったという、日本人らしい繊細な感覚の歌である。中国劉禹錫の絶句「秋風引」にも秋風によって秋の到来を知ったという同趣の詩がある。
