詩歌紹介
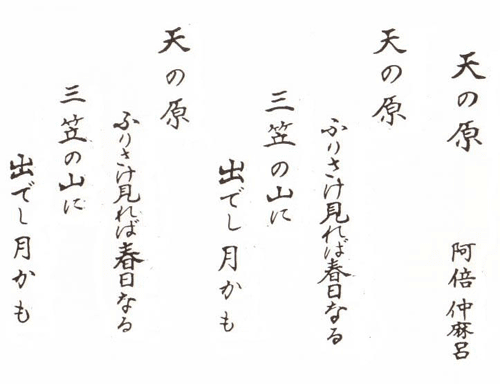
吟者:小坂永舟
2017年12月掲載
読み方
- 天の原<阿倍仲麻呂>
- 天の原 ふりさけ見れば 春日なる
- 三笠の山に 出でし月かも
- あまのはら<あべのなかまろ>
- あまのはら ふりさけみれば かすがなる
- みかさのやまに いでしつきかも
語意
-
- 天の原
- 大空 「原」は広い場所
-
- ふりさけ見れば
- 遠くを見わたすと 「ふり」は接頭語 「さけ」は「離」「放」の字をあて「遠くはなす」の意味
-
- いでし月かも
- 出た月であるよ 「し」は過去の助動詞「き」の連体形 「かも」は詠嘆の終助詞
歌意
広々とした大空を遥かに見晴らすと、今しも月が上ったところである。思えばまだ若かった私が唐土(もろこし)に出発する前に、春日の三笠の山の端からのぼったのも、この月なのであろう。
出典
「古今和歌集」(巻九)羇旅歌(きりょか)・406
作者略伝
阿倍仲麻呂 701-770
奈良時代の遣唐留学生。霊亀2年(716)16歳で選ばれて翌、養老元年(717)吉備真備(きびのまきび)らと共に唐に留学。名を朝衡(ちょうこう)と改め、玄宗皇帝に仕えた。博学多才。
皇帝に寵遇(ちょうぐう)され、李白、王維など著名文人と交際し文名があった。のち海難に帰国をはばまれて果たさず在唐50余年。その間、節度使として安南に赴き治績をあげた。宝亀元年(唐の大暦5年)唐で没す。
備考
奈良時代のはじめ、仲麻呂が唐の国へ留学生として渡海した時、玄宗皇帝の寵を受け、長年に亘って帰朝できなかった。我が国から藤原清河(ふじわらのきよかわ)らの使節が派遣され、到着したので、一行と共に帰国する許可を得て、明州(めいしゅう)というところの海岸に着いたとき、その地の人々が送別会を開いてくれた。その時、夜になって月が感慨を深めるかのようにさしのぼったので、それを眺め て詠んだ歌である。
