詩歌紹介
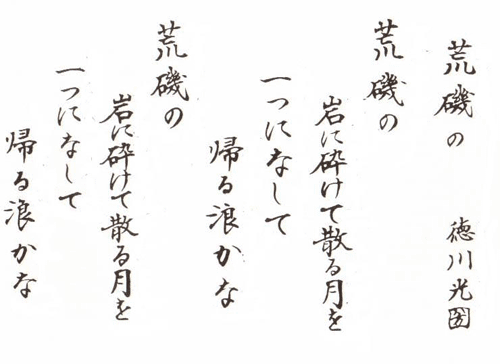
CD⑤収録 吟者:南方 快聖
2018年2月掲載
読み方
- 荒磯の<徳川光圀>
- 荒磯の 岩に砕けて 散る月を
- 一つになして 帰る浪かな
- あらいその<とくがわみつくに>
- あらいその いわにくだけて ちるつきを
- ひとつになして かえるなみかな
語意
-
- 荒磯
- 荒波の打ち寄せる磯 ありそともいう
-
- 散る月
- 水面に写っていた月が岩にぶつかった波でこなごなに砕けるさま
-
- 一つになして
- もとの形に戻って
歌意
岩に砕けては千々に散る月影、それを又、一つの月影に戻して引いて行く大いなる波よ。
出典
「常山詠草(じょうざんえいそう)」(上巻二)
作者略伝
徳川光圀 1628-1700
寛永5年ー元禄13年。江戸前期の水戸藩主。徳川家康の十一男賴房の三男。初代賴房の業を受け継ぎ、藩士の規律・諸種の勧農策(かんのうさく)・寺社の整備などを通じて藩政の安定に尽くした。文治(ぶんち)政治期の一典型として名君の誉れが高い。彰考館を設立し「大日本史」の編纂(へんさん)を開始、のちの水戸学の源流となった。有名な楠正成のための碑は光圀によって元禄5年(1692)7月摂津湊川に建立された。元禄13年(1700)12月没す。年73。
備考
打ち寄せる波に運ばれて岩にくだかれた月が、引いてゆく波にみるみる蘇ってゆくさまは、まるで時間を逆戻りさせるかのような感覚がある。難解な詞も技巧も使用せず味わい深い歌となっている。
かつて鎌倉の三代将軍源実朝が自身の心傷と重ね合わせた風景歌があるので紹介したい。
大海(おおうみ)の磯もとどろに寄する波 破(わ)れて砕けて裂けて散るかも
光圀が著した「常山詠草」は、上中下三巻に分かれ、上巻と下巻は各2冊で歌集、中巻1冊は文集である。歌集は四季・恋・雑歌に分類され、その内訳は春42首、夏12首、秋21首、冬9首、恋5首、雑47首の136首が収められている。
