詩歌紹介
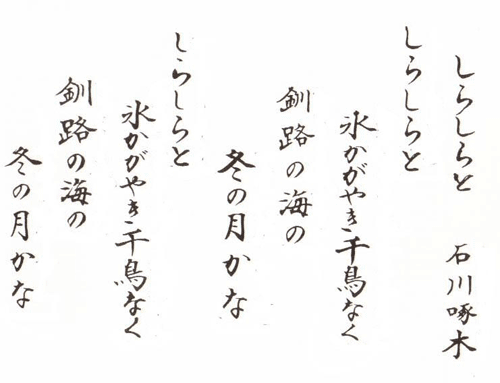
CD⑤収録 吟者:植田飭菖
2018年3月掲載
読み方
- しらしらと<石川啄木>
- しらしらと 氷(こほり)かがやき 千鳥なく
- 釧路の海の 冬の月かな
- しらしらと<いしかわたくぼく>
- しらしらと こおりかがやき ちどりなく
- くしろのうみの ふゆのつきかな
語意
-
- しらしらと
- 氷のかがやくさまをより鮮明にさせる語
-
- 千鳥
- 海や河に住み群れて飛ぶ鳥 姿も鳴き声も愛らしい
-
- 月かな
- 「かな」は詠嘆の意を表す終助詞で……であることよ
歌意
冬の月が釧路の海を照らしている。海岸は流氷でおおわれ、氷がしらしらと輝いている。そして千鳥のするどい鳴き声が聞こえてくる。
出典
「一握の砂」
作者略伝
石川啄木 1886-1912
明治19年ー明治45年。歌人・詩人・評論家。岩手県生まれ、名は一(はじめ)。17歳のとき、盛岡中学を中退して東京に出たが、翌年病気のため帰郷して、小学校の代用教員となる。1907年北海道に渡り地方記者を転々とし、翌年作家を志して再び上京、朝日新聞社の校正係となった。貧乏と病気に苦しめられる困難な生活の中で、社会的関心を深め、自己の苦しい生活感情を率直にうたった。また社会主義思想に関心をもったが、世に認められないうちに貧窮の中で胸を病んで早世した。年26。
備考
初出は東京朝日新聞の明治43年5月9日号の、「手帳の中より」に5首連作の2首目に「しらしらと氷かがやき千鳥なく釧路の海も思出にあり」と発表されたが、のち『一握の砂』において「海も思出にあり」を「海の冬の月かな」に改作された。「冬の月」をとりいれたことで寒冷の地にふさわしい光景が開けたが、冬の釧路に千鳥の居ないことを知っている読者には演出過剰の感が生じ、純粋な叙景詩とはいい難いと評している人もある。
