詩歌紹介
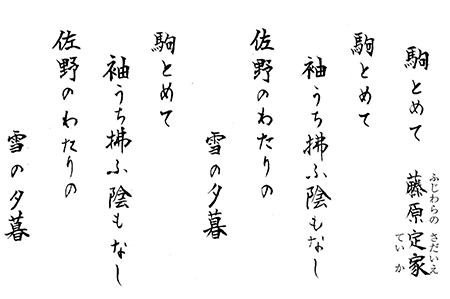
読み方
- 駒とめて<藤原定家>
- 駒とめて 袖うち拂う 陰もなし
- 佐野のわたりの 雪の夕暮れ
- こまとめて<ふじわらのさだいえ(ていか)>
- こまとめて そでうちは(ろオ) かげもなし
- さののわたりの ゆきのゆうぐれ
語意
-
- 駒とめて
- 馬をとどめて
-
- 袖うち拂ふ
- 降りかかった袖の雪を払いのける 「うち」は接頭語 「払ふ」対象は雪
-
- 陰もなし
- 物陰もない
-
- 佐野のわたり
- 「佐野」は和歌山県新宮市佐野のあたりであろうか 「わたり」は渡し場・渡船場 またはあたり・近所 ここでは佐野のあたりの意にとった
歌意
乗ってきた馬をとどめて、袖の雪を払いのける物陰も見当らない佐野のあたりの雪の夕暮れよ。
出典
「新古今和歌集」(巻六)671
作者略伝
藤原定家 1162ー1241
応保(おうほう)2年ー仁治(にんじ)2年。平安時代末期から鎌倉時代初期の歌人。
藤原俊成(としなり)の子。母は藤原親忠(ちかただ)の女(むすめ)美福門院加賀。民部卿などを経て正二位権(ごん)中納言に至り、天福元年(1233)72歳で出家、法名を明静(めいじょう)といった。父とともに新古今時代歌壇の中核的存在で、和歌所寄人(わかどころよりうど)。「新古今集」の撰者にあたった一人。老後さらに「新勅撰集」を独撰奏上した。自撰家集に「拾遺愚草」、歌論書に「近代秀歌」「詠歌大概」「毎月抄」(まいげつしょう)等があり、日記に「明月記」その他多くの編著がある。晩年は古典研究や刊本、写本の正誤を正し、後世に多くの証本を残した。仁治2年8月没す。年80。
備考
この歌は、「万葉集」の歌人、長忌寸奥麻呂(ながのいみきおきまろ)の「苦しくも 降り来る雨か 神(みわ)の崎 狭野(さの)の渡りに 家もあらなくに」を本歌として詠まれ、降る雪を避ける物陰もなく難渋している旅人としての苦しみの中にも、「雪」と「夕暮」を詠みこむことにより、静かで格調高く優美に描写されている。
