詩歌紹介
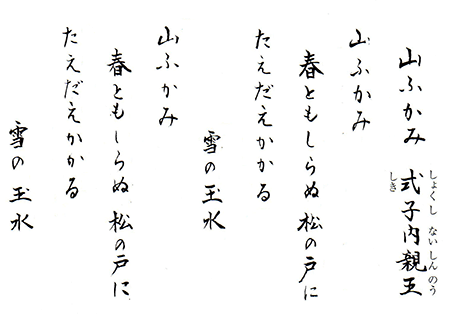
読み方
- 山ふかみ<式子内親王>
- 山ふかみ 春ともしらぬ 松の戸に
- たえだえかかる 雪の玉水
- やまふかみ<しょく(しき)しないしんのう>
- やまふかみ はるともしらぬ まつのとに
- たえだえかかる ゆきのたまみず
語意
-
- 松の戸
- 松の木で作った板戸 または松の枝を編んだ枝折り戸
-
- たえだえ
- 間隔をおいて とぎれとぎれに
歌意
山が深いので、春がきたこともわからない私の庵の松の板戸に、とぎれとぎれに雪どけ水が、玉のように輝きながらおちかかっています。
出典
「新古今和歌集」(巻一)春歌上・3
作者略伝
式子内親王 1149?-1201
鎌倉前期(久安5?-建仁元年)の歌人、後白河天皇の第三皇女、母は藤原季成(すえなり)のむすめ成(しげ)子。1159年賀茂斎院となり、1169年病により辞す。晩年出家し承如法と号す。藤原俊成を和歌の師とし、和歌に長じ新古今歌風を代表するといわれる。 簗瀬(やなせ)一雄編「式子内親王全歌集」がある。
備考
この歌は1200年(正治2年)式子内親王逝去前年51歳の時、後鳥羽院に詠進した「正治初度(しょど)百歌集」の一首で、老境の中でかすかな春の到来を喜ぶ和歌である。身は、はなやいだ春光の中での生活ではなく、賀茂斎院から、父法皇の崩御後に至るまではとくにさびしい生活であった。庵の板戸にとぎれとぎれにかかる雪どけの水が輝いているのを静かな心で見ている。それは遁世者に近いものであったろう。
