詩歌紹介
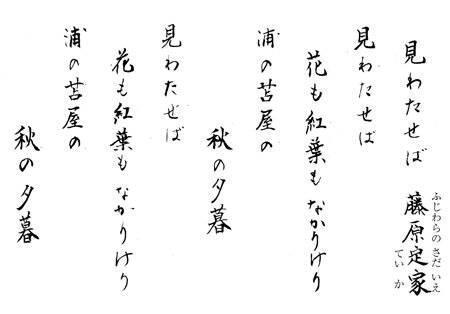
読み方
- 見わたせば<藤原定家>
- 見わたせば 花も紅葉も なかりけり
- 浦の苫屋の 秋の夕暮れ
- みわたせば<ふじわらのさだいえ(ていか)>
- みわたせば はなももみじも なかりけり
- うらのとまやの あきのゆうぐれ
語意
-
- 浦
- 入り込んだ海岸
-
- 苫屋
- 漁夫の住む粗末な仮小屋 「苫」は菅(すげ)・茅(かや)・わらなどで編んだもの
歌意
見わたすと、美しい春の桜も、色とりどりの秋の紅葉も何もない。海辺に苫屋だけが見える秋の夕暮れよ。
出典
「新古今和歌集」(巻四)秋歌上・363
作者略伝
藤原定家 1162ー1241
応保(おうほう)2年ー仁治(にんじ)2年。平安時代末期から鎌倉時代初期の歌人。
藤原俊成(としなり)の子。母は藤原親忠(ちかただ)の女(むすめ)美福門院加賀。民部卿などを経て正二位権(ごん)中納言に至り、天福元年(1233)72歳で出家、法名を明静(めいじょう)といった。父とともに新古今時代歌壇の中核的存在で、和歌所寄人(わかどころよりうど)。「新古今集」の撰者にあたった一人。老後さらに「新勅撰集」を独撰奏上した。自撰家集に「拾遺愚草」、歌論書に「近代秀歌」「詠歌大概」「毎月抄」(まいげつしょう)等があり、日記に「明月記」その他多くの編著がある。晩年は古典研究や刊本、写本の正誤を正し、後世に多くの証本を残した。仁治2年8月没す。年80。
備考
建仁元年(1201)、後鳥羽上皇から和歌集勅撰の院宣(いんぜん)が下された。撰者はその年再興された和歌所寄人の源通具(みなもとのみちとも)・藤原有家(ふじわらのありいえ)・藤原定家(ふじわらのさだいえ)・藤原家隆(ふじわらのいえたか)・藤原雅経(ふじわらのまさつね)・寂蓮(じゃくれん)の6人である。(寂蓮は翌年没したので実際は5人)。
「三夕(さんせき)の歌」=新古今和歌集の中で結句が「秋の夕暮れ」となる3首
さびしさは その色としもなかりけり 槙(まき)立つ山の 秋の夕暮れ 寂蓮法師
心なき 身にもあはれは知られけり 鴫(しぎ)立つ沢の 秋の夕暮れ 西行法師
見わたせば 花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ 藤原定家
