詩歌紹介
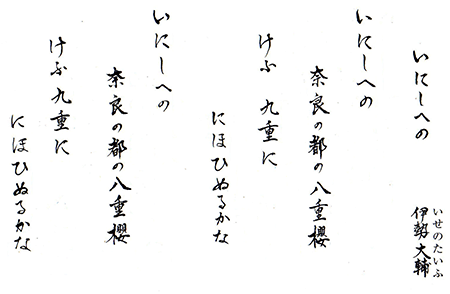
読み方
- いにしへの<伊勢大輔>
- いにしへの 奈良の都の 八重櫻
- けふ 九重に にほひぬるかな
- いにしえの<いせのたいふ>
- いにしえの ならのみやこの やえざくら
- きょう ここのえに においぬるかな
語意
-
- いにしへ
- かつて 昔
-
- 奈良の都
- 元明天皇から光仁天皇まで七代の天皇が都とされた
-
- 八重櫻
- 花弁が幾重にも重なり他の種の桜よりも遅く咲く
-
- 九 重
- 宮中 昔の中国王城は九重の門があったことから宮中をいうようになった
-
- にほひぬる
- 美しく咲いている 「にほひ」は美しく咲く視覚的なものをいう 香りの「匂い」とは異なる
歌意
昔、都であった奈良の(美しく咲き誇っていた)八重桜が、今はこの平安の宮中でいっそう美しく咲いていることよ。
出典
「詞歌集(しかしゅう)」(巻一)春・27(百人一首・61番)
作者略伝
伊勢大輔 生没年未詳
11世紀前半ごろの人。伊勢神宮の神官の娘で、中宮彰子(ちゅうぐうしょうし)に仕えて紫式部や和泉式部らと親交があった。後に筑前守高階成順(ちくぜんのかみたかしなのなりのぶ)の妻となる。家集に「伊勢大輔集」がある。
備考
この歌は「詞歌集」によると、奈良から宮中に献上された八重桜について、作者が一条天皇の命により御前で詠んだとされている。「八重」と「九重」との対照で、数の多い分奈良よりも京都でさらに美しく咲きほこるさまを強調している。「いにしへ」と「けふ」の対比によって、かつて栄えた奈良の都への憧れと今の平安の繁栄を謳歌する技巧のすばらしさを評価されたという。「けふ」は「今日・京」、「九重」は「宮中・ここの辺」の意の掛詞。
