詩歌紹介
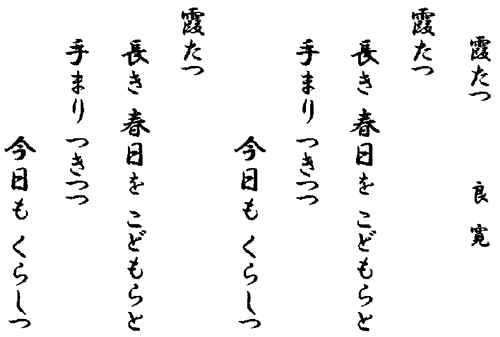
読み方
- 霞たつ <良寛>
- 霞たつ 長き春日を こどもらと
- 手まりつきつつ 今日もくらしつ
- かすみたつ <りょうかん>
- かすみたつ ながきはるひを こどもらと
- てまりつきつつ きょうもくらしつ
語意
-
- 霞たつ
- 多くは「春日」にかかる枕詞であるがこの場合はそのまま実景として訳したほうがよい
歌意
春霞のたつ、長い春の日をこどもたちと、手毬をつきながら今日も暮らしたことよ。
出典
歌集「布留散東(ふるさと)」
備考
表記の異同のうち、「今日もくらしつ」と「この曰くらしつ」の両者があるが、一般に流布(るふ)している方を採用した。
参考
良寛と貞心尼(ていしんに)について
良寛にとって貞心尼の存在は外せない。良寛が70歳のころ、無欲無心の慈僧を慕って、30歳あまりの貞心尼という尼僧が仏道・短歌を学びたいと庵に尋ねて来た。 その後、師弟関係となり、晩年には相聞歌を交わす仲にもなった。その様子は、創作だが瀬戸内寂聴の小説「手毬」に興味深く書かれている。
作者略伝
良寛 1758~1831
江戸時代後期の僧侶。本姓は山本、幼名は栄蔵、字は曲(まがり)、出家して良寛、大愚(たいぐ)と号した。越後(新潟県)出雲崎(いずもざき)の人。家は代々神職と名主を兼ね、父泰雄は越後俳壇の雄であった。良寛は成長して備中玉鳥(たましま=岡山県倉敷市)の円通寺(えんつうじ)で国仙(こくせん)和尚に師事し、帰郷後は国上山(くがみやま)の五合庵に入り、40歳から約20年間ここに住んだ。晩年は麓の乙子(おとご)神社の庵に移り、島崎の木村家で貞心尼らに看取られて没す。俳句・短歌・漢詩・書の道にも通じていた。享年74。
