詩歌紹介
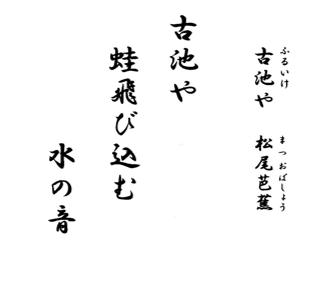
読み方
- ふるいけや かわず とびこむ みずのおと
語意
古池や=「や」は間投助詞。「初句切れ」の句で「古池や」と詠んだところで、昼間でも閑散とし、物音ひとつ聞こえない池を連想させる。
蛙飛び込む=深閑とした中で、突然かえるが池に飛び込み、そのあとまた静まりかえった池になる。
水の音=かえるが池に飛び込んだ音。周囲が静まりかえっているだけに、その音が余情を持つ。
句意
古池にかえるが飛び込んだ。ひっそりとした中に、その水音がいつまでも耳に残っている。
季語
蛙ー春
出典
「春の日」
作者略伝
松尾芭蕉 1644-1694
江戸時代前期の俳人。伊賀(三重県)上野の人。
城主一族の藤堂良忠(とうどうよしただ=俳号蝉吟=せんぎん)につかえて俳諧の影響を受け、蝉吟の死後、京都で俳諧・古典を学びさらに江戸に出て深川の芭蕉庵に住み、俳諧師として身を立てた。当時盛んだった談林(だんりん)派の俳風にあきたらず自然や人間の生活の中に古典文学の美の精神を新しく探し出した、蕉風という新しい俳風をうち立てた。元禄7年(1694)大阪にて風邪と過労が原因で客死。享年51。
備考
この句は蕉風俳諧を確立した句とされており、江戸時代から俳句の代名詞として広く知られている。
静から動への急転、動から静への還元、それが古池と蛙という物象と相まって、そこに無限の幽玄閑寂の雰囲気が漂う。
