詩歌紹介
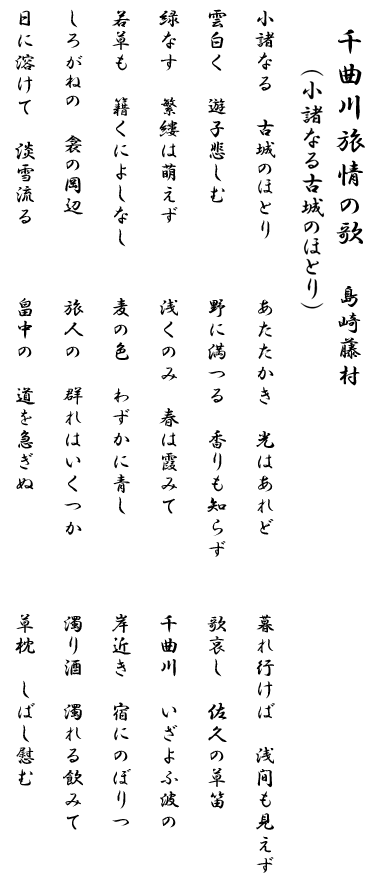
吟者:池田 菖黎、小坂 永舟
2011年9月掲載
読み方
- 千曲川旅情の歌(小諸なる古城のほとり)<島崎藤村>
- 小諸なる 古城のほとり
- 雲白く 遊子悲しむ
- 緑なす 蘩蔞は萌えず
- 若草も 藉くによしなし
- しろがねの 衾の岡辺
- 日に溶けて 淡雪流る
- あたたかき 光はあれど
- 野に満つる 香も知らず
- 浅くのみ 春は霞みて
- 麦の色 わずかに青し
- 旅人の 群はいくつか
- 畠中の 道を急ぎぬ
- 暮れ行けば 浅間も見えず
- 歌哀し 佐久の草笛
- 千曲川 いざよふ波の
- 岸近き 宿にのぼりつ
- 濁り酒 濁れる飲みて
- 草枕 しばし慰む
- ちくまがわりょじょうのうた<しまざきとうそん>
- こもろなる こじょうのほとり
- くもしろく ゆうしかなしむ
- みどりなす はこべはもえず
- わかくさも しくによしなし
- しろがねの ふすまのおかべ
- ひにとけて あわゆきながる
- あたたかき ひかりはあれど
- のにみつる かを(お)りもしらず
- あさくのみ はるはかすみて
- むぎのいろ わずかにあおし
- たびびとの むれはいくつか
- はたなかの みちをいそぎぬ
- くれゆけば あさまもみえず
- うたかなし さくのくさぶえ
- ちくまがわ いざよふ(お)なみの
- きしちかき やどにのぼりつ
- にごりざけ にごれるのみて
- くさまくら しばしなぐさむ
語意
-
- 千曲川
- 信濃川の長野県側での名称
-
- 古 城
- ここでは小諸城のこと
-
- 遊 子
- 旅人 旅行する人 ここでは藤村自身
-
- 繁 縷
- はこべ(撫子=なでしこ=科) 春の七草では「はこべら」
-
- 衾
- 夜具 掛け布団 ここでは白銀の山並みのたとえ
-
- 淡 雪
- うっすらと降り積もった雪 春になって降る溶けやすい雪
-
- 浅 間
- 浅間山
-
- いざよふ波
- 漂う波
詩意
旅人が小諸にある古城のあたりにたたずみ、白い雲を見上げていると、旅の愁いが一層つのり悲しみが増すのである。
春まだ浅く、はこべは芽生えておらず、若草も腰を下ろすには十分ではない。
しかし、白く輝く山々のすそ野では淡雪が溶けて流れている。
あたたかい春の光はあるけれども、野に満ちる香りはなく、春霞が浅くかかっているだけで、麦の色はわずかに青い。畠の中の道を宿場へと急いでいく旅人の群れが見える。
日が暮れ浅間山も見えなくなり、草笛の音が哀しく聞こえる。旅人は千曲川の漂う波の岸に近い宿にあがり、濁り酒を飲んで旅愁をしばらくの間慰めている。
出典
「落梅集(らくばいしゅう)」
作者略伝
島崎藤村 1872─1943
明治5年、長野県馬籠(まごめ)村(現在、中津川市馬籠)に生まれる。名は春樹。藤村は号。明治・大正・昭和前期の詩人・小説家。
9歳で学問のため上京、明治学院を卒業後、明治25年明治女学校の英語教師となる。翌年、「女学雑誌」の編集に携わった時期に北村透谷(とうこく)に魅せられ「文学界」に加わり、同人として浪漫的な叙情詩を発表。東北学院の教師として赴任した仙台で明治30年に第一詩集「若菜(わかな)集」を刊行。続いて「一葉舟(ひとはぶね)」「夏草」を発表。
小諸義塾の教師として信州に赴任後、明治34年「落梅集」を発表。
小諸では詩から散文への転換期であり、明治38年上京し翌年「破戒(はかい)」を発表し、日本の自然主義の代表的作家となり、数々の著作を発表。長編「夜明け前」は高い評価を受けた。昭和18年「東方(とうほう)の門」を執筆中に71歳で没す。
備考
明治32年4月、藤村は故郷に近い小諸町にある義塾の教師として赴任してきた。この詩はその2年目の春、藤村29歳の時、小諸の懐古園(かいこえん)で詠まれたものである。右手に浅間の全貌を眺め、眼下に千曲川の曲折した流れを見下ろす絶景であった。
この川のほとりでひとり酒を汲み、暮れゆく信州佐久の風物に見入っている旅人(遊子)、それはいうまでもなく藤村である。若い旅人の胸に湧く愁い悲しむ調べが基となるこの一篇は、わが国の近代詩の歴史に永く残る傑作として広く知られている。
「落梅集」では「小諸なる古城のほとり」と「千曲川のほとりにて」の独立した二編の詩であったが、いずれも小諸の千曲川のほとりでの詩のため、昭和2年刊行の「藤村詩抄」で、それぞれ「千曲川旅情の歌」の一、二として一編にまとめられた。現在では前者を「千曲川旅情の歌」として著している文書もある。
