詩歌紹介
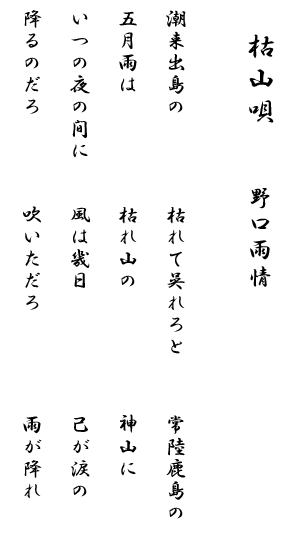
吟者:辰巳 快水
2012年2月掲載
読み方
- 枯山唄<野口雨情>
- 潮来出島の
- 五月雨は
- いつの夜の間に
- 降るのだろ
- 枯れて呉れろと
- 枯れ山の
- 風は幾日
- 吹いただろ
- 常陸鹿島の
- 神山に
- 己が涙の
- 雨が降れ
- かれやまうた<のぐちうじょう>
- いたこでじまの
- さみだれは
- いつのよのまに
- ふるのだろ
- かれてくれろと
- かれやまの
- かぜはいくにち
- ふいただろ
- ひたちかしまの
- かみやまに
- おれがなみだの
- あめがふれ
語釈
-
- 潮 来
- 茨城県霞ヶ浦の東端 行方郡(なめがたぐん)の水郷の里
-
- 常 陸
- 旧国名 茨城県の大部分
-
- 鹿 島
- 茨城県鹿嶋市 この詩ではおおまかな鹿島地方
-
- 神 山
- 明治20年頃の大字の地名 現在の大洗町(おおあらいまち)
通釈
潮来出島に降る雨は、いつの夜から降るのだろう。
枯れ山に吹く風は枯れてくれよと幾日吹いたことであろうか。
常陸鹿島の神山に、私が流す涙と同じ思いの雨よ降れ。
出典
民謡集「別後(べつご)」
作者略伝
野口雨情 1882─1945
民謡詩人。童謡詩人。茨城県多賀郡(現在の北茨城市)に生まれる。本名英吉。明治35年東京専門学校(現在の早稲田大学)を中退。3年後に日本で最初の創作民謡集「枯草」を刊行。明治40年に口語自由詩を促進する早稲田詩社を相馬御風(ぎょふう)、人見東明(とうめい)、三木露風(ろふう)らと結成。その後大正8年ころから童謡運動を推進。10年に民謡集「別後」、童謡集「十五夜お月さん」がまとめられた。その活躍は、北原白秋・西条八十(やそ)と並んで三大童謡・民謡詩人と称された。
著名な詩に「船頭小唄」「波浮の港」「赤い靴」など。
備考
≪雨情こころの変遷≫社会主義詩人であった雨情は日露戦争前後の時代に、自らを表現する事のできない限界と無力感とを味わったのではないだろうか。雨情は無力感から「枯草」と同じであるという考えに自分を見つめなおした。「枯草」の自然と、民衆とを重ね合わせる中で、強く主義主張する事のない「枯草」のような物言わぬ存在、それこそが民衆の姿である。雨情は「物言わぬ民衆の姿」を詠うことで歩むべき方向を見つけたのではないかと思われる。
