詩歌紹介
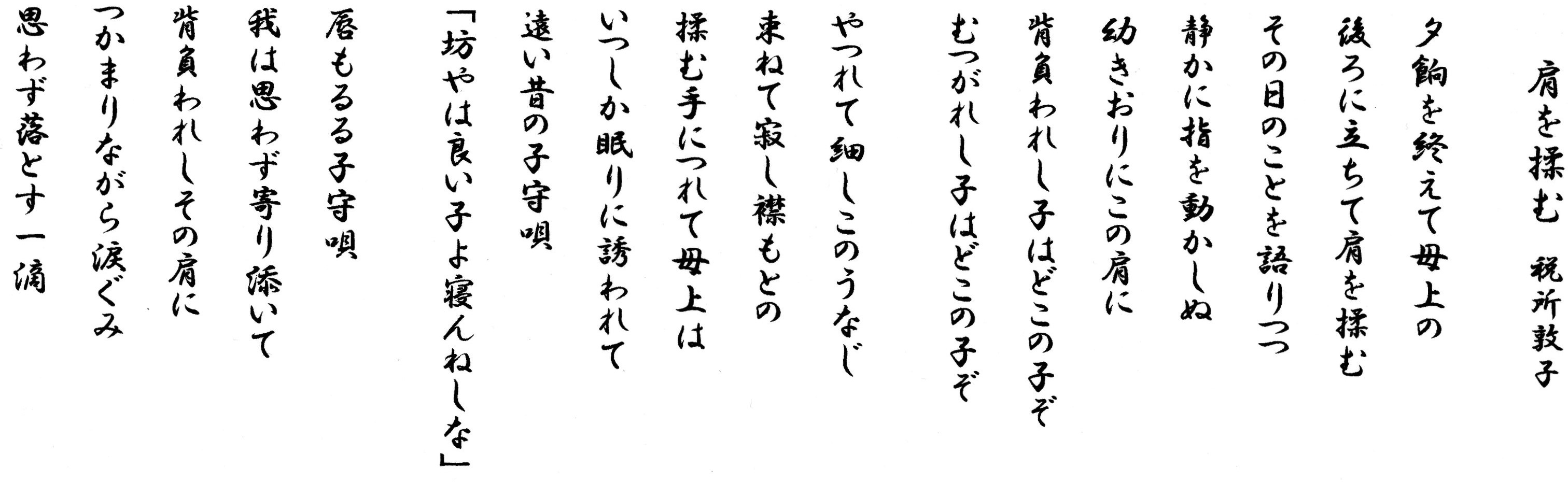
読み方
- 肩を揉む <税所敦子>
- 夕餉を終えて母上の
- 後ろに立ちて肩を揉む
- その日のことを語りつつ
- 静かに指を動かしぬ
- 幼きおりにこの肩に
- 背負われし子はどこの子ぞ
- むつがれし子はどこの子ぞ
- やつれて細しこのうなじ
- 束ねて寂し襟もとの
- 揉む手につれて母上は
- いつしか眠りに誘われて
- 遠い昔の子守唄
- 「坊やは良い子よ寝んねしな」
- 唇もるる子守唄
- 我は思わず寄り添いて
- 背負われしその肩に
- つかまりながら涙ぐみ
- 思わず落とす一滴
- かたをもむ <さいしょあつこ>
- ゆうげをおえてははうえの
- うしろにたちてかたをもむ
- そのひのことをかたりつつ
- しずかにゆびをうごかしぬ
- おさなきおりにこのかたに
- せおわれしこはどこのこぞ
- むつがれしこはどこのこぞ
- やつれてほそしこのうなじ
- たばねてさびしえりもとの
- もむてにつれてははうえは
- いつしかねむりにさそわれて
- とおいむかしのこもりうた
- 「ぼうやはよいこよねんねしな」
- くちびるもるるこもりうた
- われはおもわずよりそいて
- せおわれしそのかたに
- つかまりながらなみだぐみ
- おもわずおとすひとしずく
語句の意味
-
- むつがれし
- むずがる(憤る) 幼児が機嫌を悪くして泣く 「し」は過去を表す助動詞 駄々をこねて泣いた
鑑賞
肩を揉まれている母は義母か実母か
最大の鑑賞点は、この母が夫の母かそれとも自分の母かという点にある。「背負われし子はどこの子ぞ」と他人の子のようであるため、夫の子供時代に思いをはせているととる。つまり夫の母であろう。作者の人となりを知ると、才徳兼備とあるので、夫の死後も税所家に仕え義母にも仕えたのだろう。ある書物には、この義母はかなり意地が悪く、鹿児島で同居してある間も嫁いびりが激しく、知る人は「鬼婆あ」とひそかに悪口を言うほどであったが、作者はそれに耐え、いや「義母さまは仏さまのようです」と歌に託し、恨み事一つ言わなかったとある。貞淑で日本婦人道に適(かな)う人格者。その人が義母孝行をしているのである。
ところが義母の子守唄を聞くうち思わず自分の母親の面影が浮かび、一筋に自分を育ててくれた幼き日々のことが思い出され、懐かしく、いとおしく、自然に涙が流れたのである。つまり最後は実の母を歌っている。
この二人の母の間にいるのが作者で、したがってもうどちらの母とか区別する必要はなくなったいる。平易ながら日本人の魂に沁み込む詩である。
作者
税所敦子 1825~1900
明治初期の女流歌人
京都の宮家付武士(宮侍=みやざむらい)林篤国(あつくに)・榮子の長女として生まれる。18歳で父を亡くし、24歳で母が亡くなる。20歳で薩摩藩士・税所篤之(あつゆき)の後妻となったが、28歳で死別。のち藩候に召されて世子(諸侯の世継ぎ)の伝(取り次ぎ役)となり、明治8年、権掌侍楓内侍(ごんのないしのじょうかえでのないし=※)として宮内庁に出仕、皇后に仕えた。宮内卿や伊藤博文ともたびたび打ち合わせることもあったが、「あれほどの偉い婦人に会ったのは初めてだ」と周りの人に話していたともいわれて、人々は彼女を明治の紫式部とたたえた。
宮中にあっては、外国要人の接待に不自由であると、フランス語、英語を勉強して短時間のうちに習得している。歌を桂園派(けいえんは)の千種有功(ちくさありこと)、八田知紀(はったとものり)に学び、宮内省派の代表的女流詩人として知られた。家集「御垣の下草(みかきのしたくさ)」がある。
※=宮中には内侍司(ないしのつかさ)という役所があって、そこに属しているすべての女官を内侍
という。この役所の長官を「尚侍」と書いて「ないしのかみ」という。
