詩歌紹介
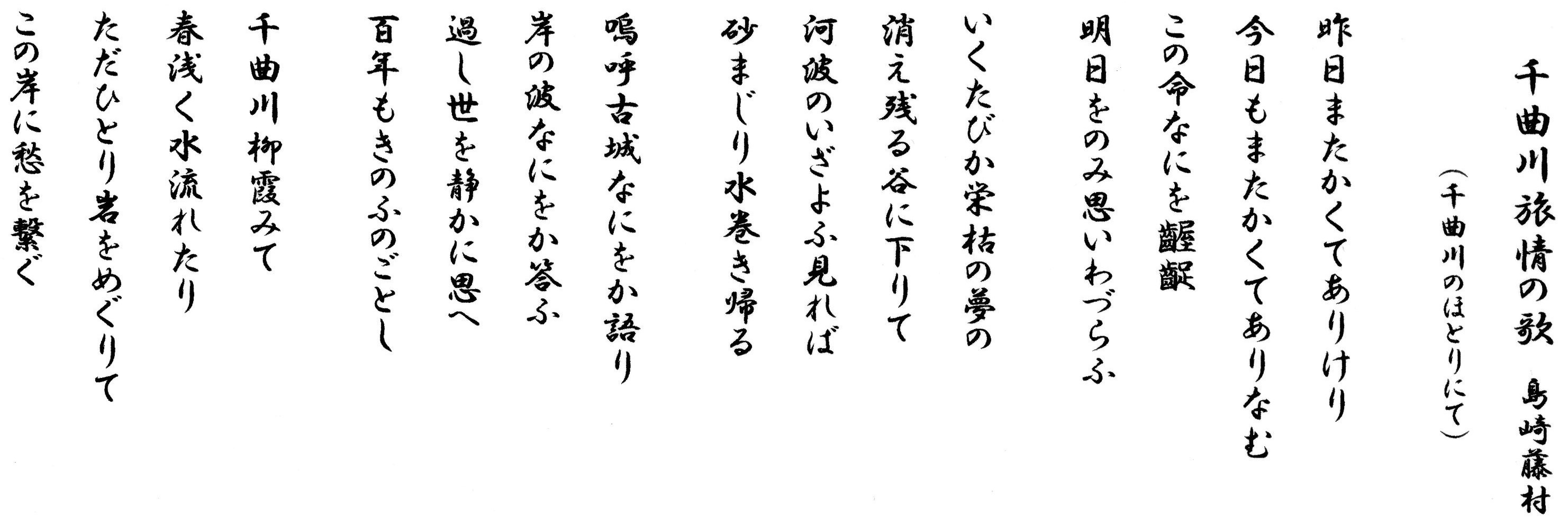
読み方
- 千曲川旅情の歌(千曲川のほとりにて)
- <島崎藤村>
- 昨日またかくてありけり
- 今日もまたかくてありなむ
- この命なにを齷齪
- 明日をのみ思ひわづらふ
- いくたびか栄枯の夢の
- 消え残る谷に下りて
- 河波のいざよふ見れば
- 砂まじり水巻き帰る
- 嗚呼古城なにをか語り
- 岸の波なにをか答ふ
- 過し世を静かに思へ
- 百年もきのふのごとし
- 千曲川柳霞みて
- 春浅く水流れたり
- ただひとり岩をめぐりて
- この岸に愁を繋ぐ
- ちくまがわりょじょうのうた(ちくまがわのほとりにて)
- <しまざきとうそん>
- きのオまたかくてありけり
- きょオもまたかくてありなん
- このいのちなにをあくせく
- あすをのみおもいわずろオ
- いくたびかえいこのゆめの
- きえのこるたににくだりて
- かわなみのいざよオみれば
- すなまじりみずまきかえる
- ああこじょうなにをかかたり
- きしのなみなにをかことオ
- いにしよをしずかにおもえ
- ももとせもきのオのごとし
- ちくまがわやなぎかすみて
- はるあさくみずながれたり
- ただひとりいわをめぐりて
- このきしにうれいをつなぐ
語句の意味
-
- 千曲川
- 信濃川の長野県側での名称
-
- 齷 齪
- 小さなことや目先のことにとらわれて気持ちが落ち着かないようす
-
- 思ひわづらふ
- 思いなやむ いろいろと考え苦しむ
-
- いざよふ
- 進まないでとまりがちになる
-
- 嗚 呼
- ものごとに感じ喜びや悲しみに心を動かして発する声
-
- 古 城
- 小諸城 今は懐古園になっている
-
- 霞みて
- 微細な水滴が空中に浮遊しぼんやりして遠くがはっきり見えないようす
詩の意味
昨日もまたいつもの生活が続き、今日もまた続いて行くのだろう。自分は小さな事にとらわれて、何をこせこせしているのだろう。明日の人生にとって大切なことをいろいろ悩みながら考えていこう。
何回か昔栄えていた跡が残る谷に下りて川の流れを見れば、波が行きつ戻りつしているようで、砂をまぜて渦を巻いている。
ああ、古城は何を語り、岸の波は何を答えているのだろう。過ぎ去った時代を静かに思うと、100年前もきのうのように短く感じられる。
千曲川の柳も霞んでぼんやりとしている。早春の川の流れのほとりを、ただひとり岩から岩へとめぐって、この流れの岸に悲しみをしっかりと繋ぎ止めておこう。
出典
「落梅集(らくばいしゅう)」
鑑賞
詩と青春への惜別・新しい旅立ち
「初恋」(若菜集)で、ういういしい生命の燃焼と自我の目覚めをうたった藤村も、まもなく20代を終えようとしている。
悩みの多かった青春の日々を回顧し、今後の生活に思いをめぐらす時、人生の愁いが重くたれこめてくる。「昨日またかくてありけり 今日もまたかくてありなむ」。ここには、もはや青春のはなやいだ気分はない。青春の炎が燃え尽きようとする悲しみと、日々の生活を問い直し、明日へと繋いでいこうとする重く沈んだ気分である。
哀愁の想いで千曲川の岸辺に立った藤村は、川の流れに人の世の移り変わりを見、古城に時の流れを見る。藤村が小諸で生活した明治30年代は、まだ幕末・維新を生きた人々が生活していた。士族と庄屋本陣として名家だった島崎家の没落を見た藤村は、自然と比べ人の世の不安定さ、はかなさを強く感じたことだろう。それでも人は、生きていかなければなだない。ようやく春めいてきた千曲川の川べりをただ一人歩きながら人生の流転の憂いを深くし、「この岸に愁を繋ぐ」と、重く静かに生きる決意を固めている。藤村は「落梅集」を最後に詩と決別し小説へと移り、近代文学史上重要な作品を数多く残す。この詩は、藤村の詩人としての最後を飾るにふさわしい優れた作品と言える。
備考
①詩題の変遷
明治33年「一小吟(いちしょうぎん)」の題名で発表された詩。その後「落梅集」(明治34年8月・春陽堂)に収録された際、「千曲川旅情の歌」と改められた。「改刷版藤村詩集」(大正6年9月)では「千曲川旅情の歌」の総題のもと、「千曲川のほとりにて」の表題で収録された。その後、藤村の自選である「藤村詩抄」(昭和2年7月・岩波文庫)では「千曲川旅情の歌二」として「小諸なる古城のほとり」と一組となり収録されている。なお本詩編の構成は、五七調四句を一連として四連から成る。
②藤村の詩作
島崎藤村の詩作は「若菜集」明治30年25歳、「落梅集」明治34年29歳の間の4年間ほどで、その短い間に新体詩を真に魅力ある文学までに高め、近代詩の母胎ともいわれる大きな業績を残した。小説に転じるのはこの後である。
作者
島崎藤村 1872~1943
明治・大正・昭和前期の詩人・小説家
明治5年、長野県馬籠(まごめ)村(現在の中津川市馬籠)に生まれる。9歳で学問のため上京、明治学院を卒業後、明治女学校の英語教師となる。翌年、「女学雑誌」の編集に携わった時期に北村透谷(とうこく)に魅せられ「文学界」に加わり、同人として浪漫的な抒情詩を発表。東北学院の教師として赴任した仙台で創作し、明治30年に第一詩集「若菜集」を刊行。続いて「一葉舟(ひとはぶね)」「夏草」を発表。小諸義塾の教師として信州に赴任後、明治34年「落梅集」を発表。小諸では詩から散文への転換期であった。明治38年上京し、翌年「破戒(はかい)」を発表。自然主義の代表的作家となり、数々の著作を発表。長編「夜明け前」は高い評価を受けた。昭和18年「東方の門」を執筆中に没す。享年71。
