漢詩紹介
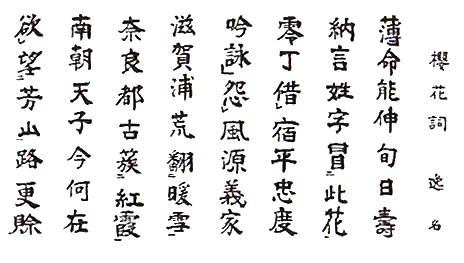
読み方
- 櫻花詞<逸名>
- 薄命能く伸ぶ 旬日の壽
- 納言の姓字は 此の花を冒す
- 零丁宿を借る 平忠度
- 吟詠風を怨む 源義家
- 滋賀の浦は荒れて 暖雪翻り
- 奈良の都は古りて 紅霞簇がる
- 南朝の天子 今何くにか在す
- 芳山を望まんと欲すれば 路更に賖かなり
- おうかのし<いつめい>
- はくめいよくのぶ じゅんじつのじゅ
- なごんのせいじは このはなをおかす
- れいていやどをかる たいらのただのり
- ぎんえいかぜをうらむ みなもとのよしいえ
- しがのうらはあれて だんせつひるがえり
- ならのみやこはふりて こうかむらがる
- なんちょうのてんし いまいずくにかおわす
- ほうざんをのぞまんとほっすれば みちさらにはるかなり
字解
-
- 能伸
- せいぜい伸びても
-
- 旬日
- 十日
-
- 納言
- 大中小納言の総称 ここでは藤原成範(しげのり)中納言のこと。この人は桜花を非常に愛し自分の館の庭に多くの桜を植えた
-
- 零丁
- 落ちぶれること
-
- 借宿
- 平忠度の辞世の歌に「ゆきくれて木(こ)の下陰を宿とせば花や今宵の主とならまし」《あても無く行くうちに日も暮れて、もし木の下に宿をとるとするならば桜の花が今宵の私を招いてくれる宿の主人となるのであろうか》(平家物語・巻九)とある。
-
- 怨風
- 源義家の歌に「吹く風を勿来(なこそ)の関と思へども道も狭(せ)に散る山桜花」《吹く風を「来てはいけない」とせきとめる勿来の関だと思うのだがその甲斐も無く風が吹いてきて道も狭くなるほど一面に散っている山桜花よ》(千載集・巻二・春・下)とある
-
- 滋賀浦
- 詠み人知らずの歌として「さざなみや滋賀の都はあれにしを昔ながらの山桜かな」《滋賀の都は今はすっかり荒れ果ててしまったけれど、昔のままに咲く長等山(ながらやま)の山桜よ》(千載集・巻一・春・上)とある
-
- 奈良都
- 伊勢大輔(だいふ)の歌に「いにしへの奈良の都の八重桜今日九重に匂ひぬるかな」《昔の奈良の都に咲いた八重桜がいま平安京の九重(宮中)にいっそう彩りよく咲いていることよ》(詞花集・巻一・春)とある
-
- 暖雪
- 桜花のたとえ
-
- 紅霞
- 八重桜のたとえ
意解
美人の薄命に似て桜花はせいぜい伸びても十日ほどの命であるが、藤原成範は(世に桜町中納言といわれたように)姓の字にこの花を仮につけている。
また平忠度も合戦に敗れ、落ちぶれて安らぐ宿を借ろうとした時の歌に「ゆきくれて・・・」というのがあるし、源義家は「吹く風を・・・」と歌って、桜の花を散らした無常の風を怨んでいる。
同じ千載集に「さざ波や・・・」とか、さらに「いにしへの・・・」など平安朝の繁栄ぶりを桜花に託して歌っている。
(ところで桜といえば吉野山、そこに都された)南朝の天子さまは今どこにいらっしゃるのだろうか。と吉野山の方角を眺めたが、道ははるかに遠いことである。
備考
この詩の作者については諸説あるが、いずれも確証はない。
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声六麻(ま)韻の花、家、霞、(貝余)の字が使われている。第一句は踏み落としになっている。第二句は二六同になっていない。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
作 者 不 詳
参考
日本に於ける漢詩の発達と代表的詩人
《第一期》王朝時代(奈良、平安時代)
遣唐船の往来により、中国の文明を摂取し、貴族を中心として栄える。
空海 嵯峨天皇 有智子内親王 島田忠臣 菅原道眞
《第二期》五山時代(鎌倉、室町時代)
鎌倉や京都の五山の僧侶を中心として栄える。
中巖円月 義堂周信 絶海中津 一休宗純
《第三期》江戸時代
武士から町人に至るまで漢詩文の教養が広まり多くの漢詩人が続出し全盛時代を迎える。
石川丈山 山崎闇齊 伊藤仁齋 伊藤東厓 新井白石 荻生徂徠
室 鳩巣 服部南郭 太宰春臺 高野蘭亭 菅 茶山 良寛
賴 山陽 篠崎小竹 藤田東湖 廣瀬淡窓 梁川星巌 佐藤一齋
吉田松陰 安積艮齋 藤井竹外
